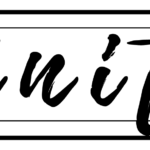ニューカレドニアのコーヒーの歴史 コーヒーの伝来と流刑植民地時代のコーヒー生産
ニューカレドニアのコーヒーと植民地化の歴史
ニューカレドニアのコーヒーの歴史と植民地化の歴史は、密接に関連している。ニューカレドニアのコーヒーの歴史において重要な時期は4つに分けることができる。これら4つの時期のうち最初の3つは、ニューカレドニアの植民地化の3つの時期に対応している。
- 植民地化の最初の試み(1856年から1911年):この時期はさらに流刑地植民地時代(1895年まで)、ポール・フェイエ(Paul Feillet)による自由植民地の形成(1902年まで)、その後のコーヒーさび病菌(L'hemileia vastatrix)の流行とロブスタ種の導入の時期(1910年)に細かく分けることができる。植民化の歴史においては、植民地形成のために試行錯誤を重ねる時期であった。
- コーヒーの繁栄と衰退(1930年から1945年):カナクの強制労働によってコーヒー産業が発展し、第二次世界大戦と土着民体制の終わりによってコーヒー産業が衰退する時期で、二つの世界大戦の戦間期と第二次世界大戦の始まりから終わりまでに当たる。植民化の歴史においては、植民地政策を維持するためにカナクを市場経済に引き入れ、経済的に支配する時期に対応している。
- 「コーヒー作戦(L'opération café)」(または、「カフェ・ソレイユ(Café soleil)」)(1978年から1992年12月31日まで) :カフェ・ソレイユとは、英語で「サン・グロウン(Sun-grown)」を意味しており、日向でのコーヒー栽培のことである。それまでのカフェ・オンブラージュ(Café ombrage)(英語で「シェード・グロウン(Shade-grown)」を意味しており、シェードツリーを用いた日陰でのコーヒー栽培のこと)からカフェ・ソレイユに栽培方法の転換を図ることによって、コーヒー産業を再生しようとした時期に当たる。植民化の歴史においては、独立を目指すカナクを再び市場経済に組み込むことによって、政治的危機の封じ込めと農村地域の雇用の創出を目的とした時期に対応している。
- 現在:レユニオン島とニューカレドニアで栽培されているブルボン・ポワントゥ(Bourbon Pointu)(または、フランス語でルロワ(Leroy)。ラウリナ、リロイ、ローリナとも呼ばれるが、ここではルロワで統一する)の栽培によって、量から質への転換を目指す時期に当たる。
ここでは、流刑地植民地時代の1894年までのニューカレドニアのコーヒーの歴史を見ていく。
コーヒーの伝来
ニューカレドニアのコーヒーの歴史は、1856年初頭、マリスト修道士がレユニオン島のアラビカ種を現在のニューカレドニアの首都であるヌメア(Nouméa)(当時のポール=ド=フランス(Port-de-France))の近く、 ラ・コンセプション(La Conception)に持ち込んだことから始まる。コーヒーを持ち込んだのがマリスト修道士であったのは、マリストが植民地の政治的権威と協調的な関係にあったことが理由であると考えられる。
植民地の政治権力と近かったマリストに対し、1902年から25年にわたってニューカレドニアで宣教活動に従事したモーリス・レーナルト(Maurice Leenhardt, 1878 - 1954)は、ウアイルー(Houailou)に「ド・ネヴァ(Dö nèvâ)(本当の国)」と名付けた伝道所を設け、植民地政策によって奪われたカナクの生活を立て直すことに奔走した。レーナルトは、コーヒーを用いた比喩によって、植民地化の問題を鮮やかに表現した。
宣教師と同様に、牧師も大首長や小首長と同じように、少しずつ植民地政策の補助者になっていく傾向がある。民主主義国の政権に協力するという単純な問題であれば、ごく普通のことでしかない。しかし、それは依存状態の永続化、ある民族を他の民族に虐待的に従属させることであった。モーリス・レーナルトの驚くほど決定的な表現によれば:「入植者のコーヒーが拾い集められている限り、土着民のコーヒーは滅びよう」というものだった。 主人の生活水準は、使用人の屈辱の上に成り立っていたのだ。レーナルトとレイ・レスキュールが去ったことで、おそらく無意識のうちに、彼らの後継者によって、受け入れられた状況に対してプロテスタントの宣教師が声を上げることはなくなった。
Comme le missionnaire, le pasteur tend à devenir peu à peu l’auxiliaire de la politique coloniale au même titre que grands et ’petits chefs. S’il s’agissait de la simple, collaboration avec l’administration d’un pays démocratique, il n’y aurait là rien que de très normal. Mais il s’agissait alors de la perpétuation d’un état de dépendance, de la sujétion abusive d’un peuple à un autre. De ce qu’en définitive exprimait de manière frappante Maurice Leenhardt : « Périsse le café des indigènes pourvu que soit ramassé celui des colons. » Le niveau de vie des maîtres était fondé sur I‘abaissement des serviteurs. Leenhardt et Rey Lescure partis, plus aucune voix missionnaire protestante ne s’éleva contre une situation acceptée, peut-être incònsciemment, par leurs successeurs.
Jean Guiart(1959)"Destin d'une église et d'un peuple : Nouvelle-Calédonie 1900-1959 : étude monographique d'une oeuvre missionnaire protestante"p.18
しかし、レーナルトもまたマリストと同様に、カナクの経済的自立を促すためにコーヒー栽培を推奨した。
当局の推進の下で、この時期に非常に重要な経済変革が行われたが、それはそもそも、ある観点から、リル・デ・パンのペール・マリストとフレール・マリスト、そして後にモーリス・レーナルト、どちらか一方の宣教師によって様々な時期に行われた努力に沿うものだった。 メラネシア社会の物質的な発展を望んでいた人々にとっての本質的な問題は、彼らに金銭的な生存手段を提供することだった。 ヨーロッパの植民地化によってコーヒー栽培の価値が明らかになった国、少なくともグランド・テール島では、他の場所を探す必要がなかった。 モーリス・レーナルトは、先住民が生産者となり、したがって経済的に自立した役割を果たせば、上役が彼らをより配慮して扱うことを決心するだろうと期待して、できる限りコーヒー栽培を奨励した。
Sous l’impulsion de l’administration, il se produisit à cette époque une transformation économique très importante, bien dans la ligne, d'ailleurs, à certains points de vue, de l’effort fait à diverses époques par l’une ou l’autre mission : en premier lieu les Pères et Frères Maristes à l’Ile des Pins, et plus tard Maurice Leenhardt. Le problème essentiel pour qui désirait un progrès matériel de la société mélanésienne était celui de lui donner des moyens monétaires d‘existence. Dans un pays où la colonisation européenne avait montré l’intérêt de la culture du caféier, il n’était, sur la Grande Terre du moins, pas besoin de chercher ailleurs. Maurice Leenhardt encouragea tant qu’il put la culture du café, espérant qu’une fois l’autochtone producteur, et donc jouant un rôle autonome sur le plan économique, on se résoudrait en haut lieu à le traiter avec plus de considération.
Jean Guiart(1959)"Destin d'une église et d'un peuple : Nouvelle-Calédonie 1900-1959 : étude monographique d'une oeuvre missionnaire protestante"p.32-33
ニューカレドニアは他の場所に比べ遅れて植民地化されたため、アラビカ種のコーヒーが導入された最後の場所の1つとなった。フランス領においては、1722年にフランス領ギアナ(Guyane française)で栽培が開始(その後、1727年に、ポルトガル海軍士官フランシスコ・パルヘッタ(Francisco de Melo Palheta, 1670 - 1750)によって、ギアナのコーヒーの苗木がブラジルに持ち込まれる)、1723年からフランスの海軍士官ガブリエル・ド・クリュー(フランス語:Gabriel-Mathieu François d'Erchigny de Clieu, 1687 - 1774)によってパリ植物園のコーヒーの苗木がマルティニーク(Martinique)へと持ち込まれ、1726年にグアドループ(Guadeloupe)へ持ち込まれた。ニューカレドニアにおけるコーヒーの導入は、それから1世紀以上も遅れることとなった。
コーヒーの最初の導入は、フランスによるニューカレドニアの領有からわずか3年後のことであった。コーヒーが導入されたことは人目を引かず、コーヒーの最初の収穫はこの地域周辺の入植者たちと共有された。
フランスによって植民化されたニューカレドニアには、フランス本国から総督府の官吏、海軍軍人、商人、開拓のための入植者、あるいは凶悪犯、共産主義者などの流刑者と、様々な境遇の人々がやってきて定住した。
この植民地化の初期段階は、どのように植民地化するのか体系化も組織化もされていない模索の時期だった。そのため、植民地支配と開発のための主要な換金作物に何を選ぶのかも定まっておらず、しばらくは試行錯誤の時期が続くことになった。
コーヒー生産の始まり
1862年、入植者のチェヴァル(Cheval)が、セント・ビンセント(Saint-Vincent)にコーヒーノキを植えた。また、同じ1862年に、農学者アドルフ・ブータン(Adolphe Boutan)が、サン・ルイ(Saint-Louis)のヤウエ(Yahoué)の13ヘクタールで、コーヒーの苗木の栽培を始めた。ヤウエは、ブータンが様々な作物の栽培と動物の飼育を試みる目的で設立した300ヘクタールの試験農園で、フランスの農学者であるマチュー・デ・ドンバール(Mathieu de Dombasle, 1777-1843) がロヴィル=ドゥヴァン=バイヨン (Roville-devant-Bayon)に設立したモデル農園に触発されたものだった。
2年後の1864年に、ヤウエで栽培された6万本のコーヒーの苗木が、主にグランド・テール島(Grande-Terre)のカナラ(Canala)に定住する入植者に栽培のために配布された。1865年には、白い花のついたコーヒーノキの枝が役所に展示され、ヌメアの人々に広く知られることになった。そして、同じ1865年に入植者のウルム(Ulm)が島で最初の商業コーヒーを販売した。
1862年にニューカレドニアの総督に任命されたばかりであったフランスの探検家シャルル・ギラン(Charles Guillain, 1808 - 1875)は、ニューカレドニアに小さな私有地の設立することによって農業社会を作り、この流刑植民地を自由植民地に発展させようとした。彼はこの政策のためにコーヒーを利用した。
19世紀後半のヨーロッパ帝国主義は、植民地の開発と支配の道具として新しい換金作物を探していた。それによって、植民地の政治的支配だけではなく、経済的開発と支配が可能となるからである(その代表的な作物の1つがコーヒーである)。1880年代までは、ニューカレドニアはコーヒー栽培ではなく、レユニオン島のクレオールの影響を受け、砂糖やラム酒製造のためのサトウキビ栽培のほうが盛んであった。それは、グランド・テール島の南西部のいたるところで栽培された。
1864年に設置された刑務所行政によって、サトウキビ栽培(さらにはトウキビとインゲン豆の栽培)が入植者に強制された。そのため、ニューカレドニアはレユニオン島やモーリシャス島のようにサトウキビ栽培で有名になるはずだった。
レユニオン島とグランド・テール島は、1862年から1870年までニューカレドニアの総督であったギランが、数回レユニオン島に寄港し、レユニオン島の人々と関係を持ったことに由来する。最初はレユニオン島の困窮したクレオールたちが、ニューカレドニアへ個人的に入植したが、1863年とその翌年にインド人労働者が集団で来島した。彼らのほとんどがサトウキビ栽培と製糖工場で働いた。レユニオン島とグランド・テール島のサトウキビ産業は深い関係を持っている。ギランの斡旋により、レユニオン島の有力な製糖業者が、製糖工場に必要な機械、技術者、労働者を携えて、グランド・テール島に移住して来たのである。
ブルボン・ポワントゥ(ルロワ)
このような流れの中で、ブルボン・ポワントゥ(ルロワ)もまたレユニオン島からニューカレドニアに導入されたが、最初はほとんど誰の注意を引くこともなかった。この品種のニューカレドニアへの導入の正確な時期は不明だが、1875年頃レユニオン島から持ち込まれたと考えられている。
アラビカ種と並んで忘れてはならないのが、その交配種のひとつである「ルロワ」である。これは、アデンに行ってアラビカ種を採取し、ブルボン島に持ち帰った船長の名前に由来する。そのため、「ブルボン・ポワントゥ」という名前でも呼ばれる。おそらく、1875年頃にレユニオン人がニューカレドニアに持ち込んだものと考えられる。そのため、砂糖と同時期に導入された。しかし、島に普及したのは、20世紀初頭、フェイエ総督の植民地化実験の少し後に遡るらしい。その後、東海岸のほとんどのコーヒー産地(ドチオ、ニンバイ、イヤンゲーヌ等)でアラビカに取って代わり、ヘミレイア・ヴァスタトリクス危機前の1910年頃には、すでに多くの場所でルロワがアラビカ種を凌駕していた。1912年の危機は、それを否応なしに衰退させ、回復することはなかった。
Avec l'Arabica nous ne saurions omettre de citer un de ses hybrides, le Leroy, ainsi nommé du nom de ce capitaine qui l'allant quérir à Aden, le ramena à l'île Bourbon. D'où son nom aussi de Bourbon Pointu. Selon toute vraisemblance, ce furent les Réunionnais qui, vers 1875, l'introduisirent en Nouvelle-Calédonie. Il serait ainsi contemporain de la phase sucrière. Mais son extension dans l'île ne semble dater que des premières années du xxe siècle, peu après l'expérience de colonisation du gouverneur Feillet. C'est alors qu'il supplanta l'Arabica dans la plupart des vallées caféières de la côte Est (Dothio, Nimbaye, Hienghène...) au point que vers 1910, avant la grande crise de l'hémileia, en bien des endroits déjà, le Leroy l'emportait sur l'Arabica. La crise de 1912 le décima inexorablement et il ne devait jamais s'en relever.
Alain Saussol(1967)"Le café en Nouvelle-Calédonie. Grandeur et vicissitude d'une colonisation"p.279-280.
レユニオン島とグランド・テール島の関係は、主にサトウキビ産業を通じて発展した。この関係を通じて、レユニオン島のコーヒーがグランド・テール島に持ち込まれたのではないか。また、1869年11月17日にスエズ運河が開通し、レユニオン島のコーヒー栽培が衰退、代わりにサトウキビ栽培が盛んになったために、コーヒー栽培をグランド・テール島で発展させようとしたのではないか、と推測できる。
コーヒー生産の鈍い拡大
サトウキビ産業が盛んになることによって、コーヒーの存在はほとんど忘れられることになるが、それでもコーヒー栽培の様々な試みが密かに続いていた。1868年に、冒険家のパネトラ(Pannétrat)が中央アメリカ由来のコーヒーノキの栽培に成功、その1年後にギランの指令により、セイロン(現在のスリランカ)のコーヒー50キロがコーヒー生産者に配布される。この時期には他にも様々な試みがあったが、それらはほとんど無名の人々によるものだった。これらはそれぞれが別々の試みとして行われたことで、一貫した政策と言えるものではなかった。また1876年に地方で行われた最初の展示会では、まだコーヒーノキは現実的に利用価値のある植物というよりも、まだ好奇の対象として眺めるものに過ぎなかった。
しかし、バッタの被害などによるサトウキビ産業の衰退による経済的危機が発生し、1878年にグランド・テール島では反乱が起こった。1878年からニューカレドニアの総督になったジャン・バティスト・レオン・オルリー(Jean-Baptiste Léon Olry)は、この荒れ果てた状況を目の当たりにした。彼はすぐに島の再建に取り掛かった。ヌメアの市議会を再編成し、他の地域で市の委員会を設立し、商工会議所を創設し、島の地図を作成し、そして経済の復興を始めた。彼はニューカレドニアに平静をもたらすことに成功した。
オルリーが、経済の復興のために注目したのがコーヒーだった。1879年のグランド・テール島中部のブーライユ(Bourail)の農園学校(Ferme-École)には、35万本のコーヒーの苗木があり、彼はこの苗木からコーヒー産業の興そうと試みた。彼はコーヒー栽培から上がる利益を入植者たちから守り、いかに自分たちのものとするかに腐心していた。ここからサトウキビ産業が少しづつコーヒー産業に取って代わることになった。
この時期はまだコーヒーは輸出できるほどの生産量には満たず、ニューカレドニア国内で消費されていた。入植者たちは畜産を主な生業とし、コーヒー生産はほとんど園芸目的のような有様だった。彼らはコーヒーノキの間に他の食物を間作していたため、コーヒー農園はより園芸用の庭のように見えた。
1880年代後半には、コーヒー栽培は約60ヘクタールを占め、地元市場への供給だけでなく、コーヒー価格の高騰により、幾分か輸出されるようになった。入植者たちのコーヒー栽培は、大部分はカナクの低コストの労働力による強制労働に依存していた。カナクに強制労働をさせる限り、入植者たちはコーヒーを育てることができたのである。
1897年に流刑者の処罰制度は廃止され、彼らは自由入植者となった。ニューカレドニアが流刑植民地であった頃には、様々な政治犯が送られてきた。1871年のパリ・コミューン(英語:Paris Commune、フランス語:Commune de Paris)が起きた後は、約3千人が送られ、処罰制度が廃止された頃には、流刑者の数は約3万人にも及んでいた。
流刑者の解放とカナクの強制労働もあり、19世紀の終わりにはニューカレドニアのコーヒー生産は高い収益性をあげることができた。ここからニューカレドニアにおけるコーヒー生産は、政治的な目的に利用されることになる。1894年にニューカレドニアの総督に任命されヌメアに到着したポール・フェイエ(Paul Feillet)は、コーヒー生産を、フランスから移民を呼び寄せ、この地を南方のフランス、美しく民主的な土地として作り上げようとした彼の目的に利用したのである。