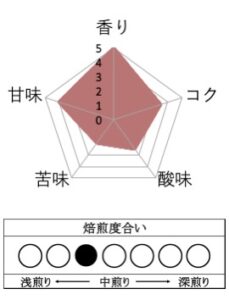ボブ・コノリー「ハイランド三部作」とジョー・リーヒのキリマ農園
『ファースト・コンタクト』
19世紀に宣教師やヨーロッパ人がニューギニアの海岸に定住してから長い間、山岳地帯の内陸部は未踏のままだった。1920年代までは、島の東西を貫く山々は険しすぎて誰も住めないと部外者は信じていた。しかし、40マイル内陸で金が発見されると、探鉱者たちは幸運を求めて珊瑚海を越えて北上した。その中に、オーストラリアのクイーンズランド州から来た3人の兄弟がいた: アイルランド移民の子供たちであるマイケル・リーヒ(Michael Leahy)、ジェームス・リーヒ(James Leahy)、ダニエル・リーヒ(Daniel Leahy)の3人兄弟で、彼らは1930年代初め、海岸から来た先住民の人夫とガン・ボア(Gun Bois)(武装兵団)の一団とともに尾根の頂上までハイキングに出かけた。
リーヒが発見したハイランドには、広く肥沃な渓谷があり、庭が整備され、後に100万人の住民が何百もの部族や氏族に分かれて暮らしていると推定された。ハイランドの人々は木材とクナイ草でできた小屋に住み、石器を使い、木の槍と矢で戦った。白人入植者たちが彼らの存在を知らなかったように、ハイランドの住民たちも山の向こうに人が住んでいるとは知らなかった。
当初、彼らは白人たちを精霊か、あるいは地上に現れた稲妻ではないかと疑っていた。恐怖よりも好奇心が強かった彼らは、鋼鉄の斧や貝殻(海岸には豊富にあるが、ハイランドでは希少で非常に珍重される)と引き換えに、サツマイモや豚、女性などを白人と交換した。探検隊が新しい部族に遭遇すると、長兄でリーダーとして認められていたマイケル・"ミック"・リーヒ(Michael “Mick” Leahy)は、自分の優れた火力を示すために豚を撃った。部族の「大物」が自分の戦士たちを集めて襲撃隊を作ろうとすれば、ミックと彼のガン・ボアはそのうちの数人も撃ち殺した。
1933年、現在のマウント・ハーゲンの近くで領有権を獲得するまで、リーヒたちはハイランドを歩き回った。そこで彼らは滑走路を作り、親切な地元の人々が延々と歌いながら土を踏み固め、小川から光沢のある岩を浚渫してささやかな富を築いた。やがてリーヒたちは内陸部を外界に「開放」したことで有名になり、マウント・ハーゲンは国内最大級の都市に成長した。
それから約50年後、当時シドニーの若いジャーナリストだったボブ・コノリー(Bob Connolly)は、オーストラリア放送協会でロビン・アンダーソン(Robin Anderson)と出会った。ふたりは恋に落ち、独立したプロジェクトを探し始めた。ある晩、たまたまニューギニアの植民地化に関するオーラル・ヒストリーの制作に携わっていた友人との夕食の席で、ふたりはミック・リーヒが探鉱者であり探検家であっただけでなく、アマチュア写真家でもあったこと、そして探検にスチールカメラとムービーカメラを持ち込んだだけでなく、彼のフィルムと写真が現存しているという噂を知った。
ロビンは、パプアニューギニアの海岸沿いの町ラエに住むミック・リーヒの息子のひとりを探し出し、屋根裏部屋に入って11本のフィルム缶を回収した。さらにロビンは、ハイランドに白人が初めて来たときのことを覚えている人々がいるという話を聞いた。シドニーに戻ったロビンは、すぐにボブとカメラ機材を携えて戻り、2人で数ヵ月かけてリーヒたちの元来た道を辿った。
ボブ・コノリーが1980年代初頭に初めてキリマ農園(Kilima Plantation)を訪れたとき、このハイランドには多くの可能性が秘められているように思えた。農園はどこまでも連なり、コーヒーの実をつけた木々は重く、広い畑には太陽の下で乾燥させた処女豆が青白く実っていた。当時、キリマのオーナーであったジョー・リーヒ(Joe Leahy)は裕福で権力を持ち、木立の手入れやパルピング工場で働くために何十人もの地元の人々を雇っていた。ガニガ族(Ganiga Tribe)の多くはやがて彼のパートナーとなり、彼らもコーヒービジネスで一攫千金を狙っていた。
ボブとロビンはハイランドで3本のドキュメンタリーを制作し、そのうちの2本は、ジョー・リーヒと彼の隣人たちを描いたものだった。それぞれが大成功を収め、いまでもそのジャンルの象徴として、人類学と映画の両方の試金石として認められている。1983年に公開された最初の作品である『ファースト・コンタクト』(原題:First Contact)はアカデミー賞にノミネートされ、最後の『ブラック・ハーベスト』(原題:Black Harvest)は「並外れた歴史的共鳴」をもたらし、「ニューヨーク・タイムズ」紙は「経済学と文化人類学のインスピレーションに溢れたクラッシュ・コースを受講しているような気分になるほど豊かだ」と書いた。「ニューズウィーク」誌は、「古典的な悲劇のスケールと豊かさを持っている」と評した。それは本当だった、すべてが最悪の結末を迎えたのだから。
ジョーの母親はジガ族(Jiga Tribe)の女性でー「石器時代の女性」と彼は好んで語ったー彼が幼児のときに亡くなった。ミックはジョーを認めなかったので、ジョーは母親の一族に育てられたが、彼はそこになじめなかった。彼の肌は薄く、髪は細く、儀式用の羽を持つことはできなかった。金鉱が途絶えてからコーヒー栽培を始めた叔父のダニー(Danny)は、ジョーが10代のときに彼を引き取り、コーヒービジネスを教え、労働から始めさせ、出世させた。
ボブとロビンが彼と出会った頃には、ジョーはキリマという自分の農園を持ち、ネビルヤー・バレー(Nebilyer Valley)で最も裕福な男の一人になっていた。マウント・ハーゲンに土地を所有し、レンジローバーを乗り回し、ベランダとフォーマルなダイニングルームのあるコンクリート・ブロックの頑丈な家に住み、前庭には巨大な衛星放送アンテナがあった。彼はトゥムル(Tumul)というガニガ族の大物から土地を安く買い、労働力のほとんどはガニガ族の人々から得ていた。彼らは彼の周囲に草小屋を建て、豚やサツマイモ畑の手入れをしながら暮らしていた。
半世紀前の出来事を描いた『ファースト・コンタクト』には、ジョーの居場所はなかった。しかし、ジョーはまさにそのような出会いの産物であり、パプアニューギニアが現代世界と出会ったときの衝撃を体現していた。「ジョーの師匠は、白人の植民地時代のオーストラリア人だった」とボブは言う。「優しさは弱さだから、決して親切にしてはいけないと教えられた。決して奴らに頭を上げさせてはいけないし、もし上げられたら叩き落とすんだ」。
ジョーが生まれながらにそういう人間だったことは、問題を複雑にしている。ジョーは別の映画の理想的な題材だった。ロビンはジョーになつかなかったが、ボブは彼を十分に気に入っていた。「いろんな意味で尊敬していたよ」。「彼はとてつもない強さ、とてつもない決意の持ち主だと思った。そして、観察ドキュメンタリー映画製作という点で、これ以上の被写体は見つからないという確信もあった。彼だけでなく、彼の置かれた状況も。物事を単純化しすぎるのは簡単だが、文化の衝突という途方もないものだった。このような物語は一生に一度しかないのだと、私は次第に悟った」。
1985年、ボブとロビンはジョー・リーヒの新作を撮るためにハイランドに戻った。彼らは1年半滞在し、ジョーの土地の藁葺き小屋に住み、カメラと音響機材を持ち歩きながら、ジョーとガニガ族の隣人との間で激化する争いのシーンを少しずつつなぎ合わせていった。ジョーはキリマとともに、共同体的な慣習の土地で資本主義的な事業を営んでいた。そこでは、土地を売買したり、富が一人の人間にもたらされたりすることは考えられなかった。実際、ガニガ族の大物トゥムルは、ジョーの白人のビスニス(Bisnis)に関する知識がトゥムルの人々も金持ちにするはずだという理由で、自分の一族のサツマイモ畑をはした金で手放していた。
『ジョー・リーヒの隣人たち』
1989年に発表された『ジョー・リーヒの隣人たち』(原題:Joe Leahy's Neighbours)の中で、ジョーはトゥムルについて「嘘ばかりだ」と憤った。「私は誰とも約束などしていない」。ジョーが本当にそう信じていたのか、これが誤解なのか詐欺なのかは、この映画からはまったくわからない。また、そんなことはどうでもよいことだ。ガニガ族は自分たちの正当な報酬を求めたのだ。
この映画の主人公の一人はジョセフ・マダン(Joseph Madang)という若い部族民で、彼はやがてボブとロビンの最も親しい友人の一人となった。「彼が80万ドル儲けたとする」。マダンはボブのカメラにこう語る。「じゃあ、俺たちも80万ドル儲けたいね。彼のものか?俺たちのものだ。彼はキリマを買ったとき、俺たちに600キナしか払わなかった。不満だよ。共同オーナーなんだ。ジョーと俺たち。彼は裕福で、今度は俺たちの番。一人の男が全財産を稼ぐのはフェアじゃない」。
ボブとロビンは1年以上にわたって、マダンがキリマを買い戻す資金を集めようとする密かな試みを撮影した。同時に、ジョーが隣人に対する義務を果たすのを見守り続けた、あちこちに数キナを配り、葬儀の贈り物をし、コーヒー泥棒を手なずける。ある時、ジョーは壊れたトラックだけでトゥムルをなだめたが、トゥムルの部族の多くは明らかに不満だった。
ついにマダンの資金調達が破綻し、ガニガ族がますます激昂するなか、ジョーはポピナ・マイ(Popina Mai)というガニガ族の大物が所有する近くの土地で、彼らがカウグム(Kaugum)と呼ぶ第二の農園を始めることに同意する。ジョーが資金を出し、部族が労働力を提供し、その利益を彼らで分配するー経済的リスクを負うと主張するジョーが60%、土地と労働力を提供するガニガ族500人が40%である。
この結末は、希望に満ちていると同時に不吉でもあり、博識と世間知らずの間の不安定な境界線をまたぐ未来への約束でもある。
『ブラック・ハーベスト』
「ハイランド3部作」として知られることになった最終作『ブラック・ハーベスト』(原題:Black Harvest)は、それから5年後、カウグムがルビーのように太ったコーヒーチェリーの初収穫に沸く頃を描いている。「価格が良ければ、金にどっぷり浸かれるだろう」。ジョーがポピナ・マイに言ったのは、植えたばかりのコーヒーの木立の中で微笑みながらこうだった。「どっぷりだ!」。
ポピナ・マイは顔をほころばせた。「俺の部族は金持ちになり、彼らは俺たちに感謝するようになるだろう」。彼は言う。「貧乏人は金持ちになり、金持ちはもっと金持ちになる」。
ボブとロビンがハイランドに戻り、また小屋を建てて新しい庭を作ったときー今度は生まれたばかりの娘を連れていたー彼らはガニガ族が新たに得た富で何をするかという映画を作ることを期待していた;カウグムの最初の作物が収穫され、果肉除去にされ、水洗され、乾燥されれば、ガニガ族の40%の取り分は数十万ドルになるはずだった。
その後、2つのことが起こった;世界市場のコーヒー価格が突然暴落したのだ。ガニガ族にとっては不可解な出来事だった。白人のビスニスであるコーヒーが、遠くの亡霊によって消し去られるのなら、何のための労働だったのだろうか?
しかし、その災難はすぐに、より身近な出来事によってさらに悪化した:部族間の戦争が勃発したのだ。同盟部族の女性数人が、谷を越えてやってきた敵にレイプされた。その犯罪には報復が必要であり、ガニガ族は直接関与していなかったが、伝統により戦いに参加せざるを得なかった。そしてボブとロビンはその渦中に身を置くことになった。
ハイランドでの部族間の戦争はほとんど芝居じみたもので、戦いは特定の時間と場所ーたとえば誰も待ち伏せできないように草を焼き払い、踏み固めた野原で予定されー主に槍と矢、大きな木の盾、そして時折手製の散弾銃を使って戦われた。一時期、ボブとロビンは戦場に道具を持ち込むこともできた。何十人もの死傷者が出た。ある時、ジョセフ・マダンは、今ではボブとロビンの大切な友人の一人だが、裏をかかれ、原始的な銃で撃たれ、鋼鉄の斧で切り刻まれ、殺された。ボブは彼の葬式で公然と泣いた。
男たちは戦い、コーヒーの値段は安すぎて賃金は上がらず、カウグムの農作物は木の上で腐りはじめた。映画は、ジョーが無力な怒りと、自分自身と彼が被後見人として両義的な目で見ているガニガ族に対する絶望の間で揺れ動く姿をとらえている。資本主義と部族主義が、彼とガニガ族を共謀させたようだった。ほとんどすべての作物がしなび、黒くなった。うんざりし、敗北したジョーは、土地を所有し、妻と子供たちを学校に通わせていたオーストラリアのブリスベンに向かった。
『ブラック・ハーベスト』のラストで、ポピナ・マイは打ちひしがれていた。彼のパートナーでありパトロンであった人はオーストラリアに行ってしまった。友人のマダンは死んだ。彼が財産と名声を賭け、部族を現代社会に導いてくれると信じていた農園は、腐ったコーヒーチェリーで覆われていた。絶望の中、彼は戦場に出て矢が当たるのを待った。
そしてカメラは小屋の中で横たわる彼をとらえた。彼の胸は矢傷の血で腫れ上がっている。足元には友人が座り、ハエを振り払っている。部屋は影と金色の光に包まれ、ボブのカメラにピエタがはめ込まれている。「彼らは俺の農園と俺を破壊した」とポピナは言う。「矢が飛んできたとき、俺は農園のことを考えた。ジョーのことも考えた。そして矢が当たった」。彼は苦笑する。「もういい。話すのは苦痛だ」。カメラは余韻を残し、周囲のコーヒー畑を切り取る。
「ハイランド3部作」はここで終わる。「他人の不幸が映画人の幸運になることはよくあることだ」とボブは言う。彼は一拍置いてこう言った。「ひどい言い方だけど、本当なんだ」。この映画はドキュメンタリーの古典となり、今でも大学の人類学や映画学科で上映されている。「ハワイ大学の人類学者で、ハイランド地域を研究しているアレックス・ゴルーブ(Alex Golub)は言う。「同時に、文化的接触という非常に単純な物語では失われがちなニュアンスも多く伝えている。道徳的な曖昧さがある。勝利に酔いしれた白人の発展が、疲弊した黒人に知恵をもたらすというストーリーは避けているが、勇敢な先住民が植民地主義に押しつぶされるというストーリーも避けている」。
ポピナの小屋でのシーンから間もなく、ボブとロビンはキリマを離れ、マウント・ハーゲン近くのゲストハウスに向かった。農園は戦場と化し、必要なものは撮り終えた。あとはトーマス・タイム(Thomas Thyme)というガニガ族の助けを借りて、台詞を翻訳するだけだった。ある日の午後、ガニガ族の一団がマウント・ハーゲンに行き、市場で野菜を買っているボブを見つけた。彼らは彼に、八の字に曲がった杖を渡した。それは、彼らの言うことが非常に重要であるということの象徴だった:敵の部族、クルガ族がボブを殺そうとしているのだ。
ボブは怯えると同時に唖然とした。彼とロビンはどちらの味方をしたこともなかった。しかし、トーマス・タイムが銃を買ったことが判明し、クルガ族はボブとロビンがその金を彼に渡したのだと考えた。彼らはこの一端をこう推測した、マダンが殺された後、ボブが泣いたと聞いていたからだ。ロビンは無事だったし、幼児の娘もいた。しかし、ボブは標的リストに載っていた。
トーマスをシドニーに飛ばして翻訳を終わらせる余裕はなかったので、ボブは金取引の友人から銃を借り、それを寝るときも近くに置いて、斧で武装した2人組の護衛を雇った。彼らはさらに数週間の仕事を急ぎ足でこなし、ボブと家族は去っていった。彼は別れを告げなかった。
ボブは今まで一度も戻ってこなかった。「正直言って、頭を吹き飛ばされたくなかったんだ」と彼は恐れながら言った。「私が去った状況を彼らが忘れているとは思えなかった」。彼はオーストラリアに留まり、ドキュメンタリーを制作し、運命的な3作目の映画制作の経験を綴った回想録『メイキング・ブラック・ハーベスト』(原題:Making Black Harvest)を執筆した。2002年、ロビンはガンで亡くなった。その後、ボブはソフィー・レイモンド(Sophie Raymond)というミュージシャンで映画監督の女性と恋に落ち、2015年に娘が生まれた。
それから間もなく、ボブは突然メールを受け取り、キリマに戻る勇気を持つほど好奇心をそそられた。元翻訳者のトーマスの息子、ジョシャイア・タイム(Joshaia Thyme)からだった。ジョシャイアは海岸沿いの首都ポート・モレスビーに住んでおり、彼の話によると、大学を卒業した最初のガニガ族だった。彼の話によると、2人目のガニガ族(女性)も大学の学位を取得したという。「私たちの指導者たちは部族間の争いから遠ざかった」とジョシャイアは書いていた。「すべてが平和になった」。
これは希望の物語なのだろうか?それを確かめるため、2016年7月、ボブはオーストラリア放送協会と組んで、彼とロビンが去ってからの変化について30分のテレビ・レポートを作成した。彼はまた、4本目の映画、つまり進歩についてのより大きな物語が作られないか、自分でも偵察するつもりだった。
ジョーは家の前、錆でかさぶたになり、もはや衛星とはつながっていない巨大な衛星放送アンテナのそばでボブと会った。握手と挨拶を交わし、久しぶりだねとつぶやいた。ジョーは愛情表現をするような男ではない。彼は現在77歳か80歳だー彼はそのどちらとも言うーこめかみに白髪のある太い黒髪はもうない。それ以外は、ボブやロビンの映画に出てきたときとほとんど同じで、毎日キリマを何キロも歩いているため、まだ頑丈に見える。
部族間抗争が始まってしばらくは、ジョーはオーストラリアに滞在していたが、数カ月も経たないうちに、妻と3人の子供たちを残して、残されたコーヒーのために戻ってきた。約5年前、ジョーは癌で死期が近いと思ったとき、成長してマウント・ハーゲンに住んでいた息子のジム(Jim)に農園を継ぐように頼んだ。ジムと彼の妻は、2年の歳月と貯蓄のすべてを注ぎ込み、木を剪定し、工場を再建した。そして、古い木に再びチェリーが実るようになった。
それからジョーは回復して戻ってきて、彼らを追い出した。彼は自分のやり方で物事を進めたかった。農園では、ボブが最初に来たときよりも100人ほど少ない数人の収穫労働者を雇うのに十分な、わずかな生産量になっている。ジョーは多角化を図り、ピーナッツやサツマイモを植え、大きな家の裏の日陰にいる豚を含めて27頭の豚を飼っている。
4作目
十数年前、ボブが『メイキング・ブラック・ハーベスト』を出版したとき、彼とロビンが後世に残すために撮影した出来事について考える時間はすでに十数年あった。本書の最後に、ボブはパプアニューギニアでの最後の夜を回想している。身の危険を感じながら、妻と幼児の娘は眠っていたが、自分は窓際で見張り、近くに銃を隠し持っていた。その銃の記憶は「今も私の中にある」とボブは書き、「あの夜の私の黒い決意は、銃口を誰かに向け、必要ならば撃ち殺すというものだった。その決意によって、私はルールを破り、天職を裏切り、観察者と参加者の境界線を越えたのだ。ニューギニアに何年いても、これほど邪魔者だと感じたことはなかった。これ以上この場所に留まる義理はないし、正当性もない。家に帰る時だった」。
今日、ボブはこれらの映画製作に費やした時間を、喜びと誇り、そして健全なノスタルジアとともに振り返っている。「あの12年間は、個人的にも仕事上でも私のハイライトだった」と彼は言う。「そして正直に言うと、あの映画は観察映画制作の驚くべき例だと思う」。
しかし、この場所の「歴史」における自分の役割や、観察者と参加者の境界線との関係における自分の立ち位置についてはー彼はもうほとんど考え終えている。彼はとっくの昔に反省のための大変な仕事をしたのだ、そして、彼がカメラを持った男以外の何者かであったという示唆は、彼にとっては重要なことではないように思える。「控えめで中立的な記録者であろうと、できる限り努力した」とボブは言う。「重要なシーンを撮影するときは、部族と接触した後の歴史的な出来事を記録しているのだと考えたものだ。さらに踏み込むこともあった。『これはアイスキュロスやソフォクレスの物語だ』と気が付けば私はこう言っていた。偉大な悲劇が目の前で繰り広げられているのに、私たちは偉大な劇作家である必要はないー私たちがすべきことは、忍耐強く、耐え忍び、目立たないようにし、干渉せず、中立を保ち、焦点を合わせることだった」。
「私たちが一緒に仕事をした部族民のほとんどは、映画やメディアにほとんど接したことがなかった」と彼は続けた。「私たちは、人々に何をすべきか、何を言うべきかを決して指示せず、行動を繰り返させることもなく、どちらかの味方をすることを徹底的に避けたー例えば、ジョーを新植民地支配の搾取者と考え、ガニガ族を植民地支配の犠牲者と考えるような。重要な出来事は常に起こっており、そのため誰もが忙しく、私たちは物事の筋書きにおいて重要視されることはなかった。しばらくすると、私たちはいわば家具の一部に過ぎなくなった。私たちの存在が展開に大きな影響を与えることはなかったと、私は純粋に信じている」。
もし後悔があるとすれば、ボブは最後のほうに自分の仕事に夢中になっていたことに気持ち悪さを感じていることを認めている。「戦争が悪くなるにつれて、私たちがどんな人間になっていったのか、少し心配がある」と彼は言う。彼は、矢で負傷したポピナ・マイを撮影し、そのシーンがどのように映し出されるかに有頂天になったことに触れているーすぐに医者に診せるのではなく。 (実際、ボブとロビンはそのシーンを撮影した後、ポピナ・マイを病院に連れて行き、ポピナはその傷から生還し、さらに数年生きた。)。「これほど説得力のある物語にロック・オンすると」とボブは言う。「創造的野心に人間性を少しゆだねてしまう。それでも、私は撮り続けてよかったと思っている。だから、好きなように解釈してくれ」。
そして未来は?ボブはすぐに4作目がないことを悟った。彼にどんな物語が残されているのだろう?キリマやカウグムのようなかつて有望視された企業が、自らの矛盾の下で崩壊した後、立ち直れなかったこと?ガニガ族の共同体文化とジョーのビスニスが共存する道を見いだせず、ー戦争が起こるまで、あるいは商品価格が暴落するまで、地殻変動でプレートが圧し潰され、一方がずれるまで圧力を高め合うように、互いに軋み合っていることを?
ボブやロビンはすでにそのような話をしたが、悲しいかな、それ以来、記録できるほどの進歩はなかった。農園の失敗だけではないーキリマではほとんど生産ができず、カウグムは灌木の緑の蔓に覆い尽くされてしまった。「徐々にただ衰退している」とボブは言う。ボブが旅した当時、マウント・ハーゲンは今にも折れそうな「コイルバネ」のような状態であり、ネビルヤー・バレーは制度的に放棄されていた。語るべき政府もなかった。道路はまだ舗装されていなかった。マウント・ハーゲンの病院では、手術室に汚水が漏れ、スタッフがストライキを起こしたばかりだった。地元の小学校はーオーストラリアの援助団体から資金援助を受けてー建設されたが、教師は3年間給料をもらっておらず、机も椅子も本もなかった。
しかし、ボブはその事実に根本的な希望を見出した。「その教師はまだそこにいた」と彼は言う。「なぜかというと、彼はガニガ族で、土地を持っていて、妻がサツマイモを栽培していた。それだけで十分だった」。そしてそれは正しかった。貧困が蔓延し、公共サービスや経済的機会が不足しているにもかかわらず、パプアニューギニアの75%は食料と住居を自給自足していると推定されている。パプアニューギニアは、政府はほとんど関係なく、国民が自活することを学んだ国なのだ。
ある意味、ネビルヤー・バレーは劣化したのではなく、単に逆戻りしただけなのかもしれない。ボブとロビンは、ジョーのグローバリゼーションの実験を目撃したが、それは古代の部族主義によって台無しにされた。ある基準から見れば、部族社会はハイランドを現代の経済的繁栄から遠ざけているように見える;しかし、別の見方をすれば、それがこの場所を支えているのだ。何千年も機能してきた共同体の伝統や慣習、そしてそれらが培った支援制度は、1世紀足らずで解体されることはない、もし解体されるべきであったとしても。
「それが」とボブは言う。「この場所の救いなんだ」。
<映画>
PNG Highlands Trilogy:https://vimeo.com/ondemand/102205
<参考>
"The Reckoning",Smithsonian Magazine 2018年3月.