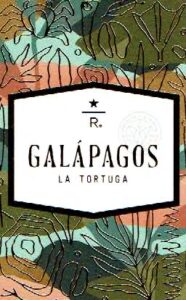コーヒーのガリシズムとジャポニズム
ガリシズムとジャポニズム

「ガリシズム(Gallicism)」とは、フランス語に残るゴール語の影響を示す言葉であり、転じて他国語に見られるフランス語法を意味する言葉として用いられる。様々な言語に見られるガリシズムは、フランス文化の帝国主義的支配力を物語っている。
「テロワール(Terroir)」や「ミクロクリマ(Microclimat)」は、ワイン用語から借用したコーヒーにおけるガリシズムである。ミクロクリマがマイクロクライメイト(Microclimate)と英語で呼ばれるのに対し、テロワールはフランス語特有の概念である。そのため、土地と品質の不可分な結びつきを意味するテロワールは、フランス語、およびフランス文化の歴史と不可分な結びつきを持つガリシズムとして機能する。
テロワールやミクロクリマが他国語に見られるフランス語法であれば、「ハンド・ドリップ(Hand drip)」や「ハンド・ピック(Hand pic)」は日本語に見られる多国語法と説明できるだろう。この日本語法を「ジャポニズム(Japonism)」と呼ぶことにしよう。
ジャポニズムという造語は、もちろん既存の美術用語の借用であり、極東は西からやってきたあらゆるものが流れ着く果てであるというオリエンタリズムを含んでいる。日本のような「表象の帝国(L'Empire des signes)」(ロラン・バルト)は、ガリシズムを嫌悪する「ジョン・ブル(John Bull)」のような確固たる意味を持たず、代わりに「サムライ(Samurai)」のようなオリエンタリズムによって偽装された記号があるのみである。そのため、日本の文化は、フランスのように自らの文化の力で他国に優越することなく、様々な舶来品を雑居させることに優れている。この意味で、ジャポニズムは外来語を日本の文脈に雑居させる方法であり、意味から解放された自由である、と評価するのは皮肉にすぎるだろうか?
フランス語の英語への影響に関して19世紀半ばに書かれた見解において、イギリス女王エリザベス1世のギリシャ語、およびラテン語家庭教師、そして教訓書家であるロジャー・アスカム(Roger Ascham)が1545年に著した『トキソフィラス(Toxophilus)』の英語の表現方法に関する文章が最後に引用されている。
Many English writers have not done so, but using strange words, as Latin, French, and Italian, do make all things dark and hard. Once I communed with a man which reasoned the English tongue to be enriched and increased thereby; saying, who will not praise that feast where a man shall drink at a dinner both wine, ale, and beer. Truly, quoth I, they be all good, every one taken by himself alone, but if you put malmsey and sack, red wine and white, ale and beer, all in one pot, you shall make a drink neither easy to be known, not yet wholesome for the body.
Sharpe's London Magazine of Entertainment and Instruction, for General Reading, A.Hill, Virtue, and Company, 1848
ここでは食卓に並ぶ飲物が、様々な言語の比喩として登場する。ワイン、エール、ビールが並ぶ饗宴のように、浅煎りのエスプレッソから深煎りネルドリップまでが並ぶ日本のコーヒー文化を誰が賞賛しないだろうか?彼らの饗宴には、対話すら存在しない。しかし、様々に異なった飲物が出揃うが、それら「すべてがひとつのポットの中に(all in one pot)」入り混じることのないこの「棲み分け」(今西 錦司)の方法は、はたして多様性を維持する優れて現代的な方法なのだろうか?
*ルソー的に言えば、テロワールを生み出す「土地や気候や季節の相異」こそが、人間の不平等の起源と言えるだろう。
人類が拡大してゆくにつれ、人間とともに苦痛が増大していった。土地や気候や季節の相異が、彼らの生活様式に相異を生じるように強いたかも知れなかった。なにもかも滅ぼし尽くす、不毛の年月や長く厳しい冬や燃えるような夏が、彼らに新たな工面工夫を要求した。海や川の沿岸では、彼らのは糸と針とを発明し、漁夫となり魚食民族となった。森のなかでは彼らは弓と矢とをつくり、狩人となり、戦士となった。寒い地方では、彼らは自分の殺した動物の毛皮を身にまとった。雷や火山、あるいは何かの幸運のおかげで彼らは火を知り、それが冬の烈しさに対する新しい対策となった。彼らはこの元素を保存すること、ついでこれを再生産すること、最後に、いままで生のままむさぼり食べていた肉を調理することを学んだ。
このようなさまざまな存在を人間自身に、また相互にくり返し適用した結果は、当然に、人間の精神のなかにある種の関係の知覚が生ぜずにはいなかった。大小、強弱、遅速、臆病、大胆などの語やその他必要に応じて比較され、しかもほとんどそうする気もなくて比較される同じような観念によってわれわれが表現するこれらの関係は、ついに彼の心のなかに、ある種の反省を、あるいはむしろ無意識の用心深さを生みだしたが、それが彼の安全にもっとも必要な注意を彼に教えてくれた。
ルソー『人間不平等起源論』,岩波文庫.p.87
*余談として、ミル・フェイユ(Mille-feuille)(千枚の葉)をミル・フィーユ(Mille fille)(千人の娘)と呼ぶのは、ガリシズムではなくマラプロピズム(Malapropism)である。
<参考>
「民俗で考えるコーヒー」,帰山人の珈琲漫考<https://kisanjin.blog.fc2.com/blog-entry-1378.html>
「ローストビーフと菜食主義 : イギリス・ロマン主義時代の食の政治と倫理」,名古屋経済大学人文科学研究会 人文科学論集 39 2019. No. 98. 39-50<https://nue.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=392&item_no=1&page_id=32&block_id=39>