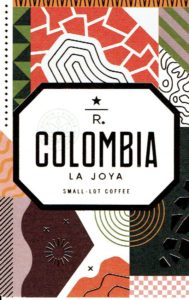スターバックスと日本
1995年10月アメリカのスターバックスコーヒーインターナショナル社は日本の小売業社である株式会社サザビー(現株式会社サザビーリーグ)と業務提携を結び、スターバックスコーヒージャパン株式会社を設立。スターバックスは世界進出の足掛かりとして、1996年8月に銀座松屋通りに日本一号店を初出店した。
お店は全面禁煙、エスプレッソやラテ、フラペチーノのような自宅では作ることが難しいシアトル系コーヒーの多様なメニューが人気を博した。スターバックスがスポーツ新聞を広げ、タバコを吸うおじさんが行くところといった従来の喫茶店を、お洒落で自分らしいライフスタイルを演出できる「サードプレース」としてのカフェにイメージを刷新したことで、特に流行に敏感な女性や若者たちを惹きつけた。
実のところ、スターバックスは銀座に一号店を出す前、スターバックスが株式公開した1992年にアメリカ大手ホテル業社マリオット・インターナショナルの出資を受け、新東京国際空港(現・成田国際空港)に出店したが、一年も経たないうちに撤退しているため、実際のところは再出店である(このことはスターバックスのホームページの沿革にも書かれていない)。
イタリアではちょうど同じ頃、1994年にアメリカのテキサス出身のトム・フォード(Tom Ford,1961-)がグッチのクリエイティブディレクターになり、華美なデザインと斬新な広告とでグッチの再建に乗り出していた。
この頃生まれたクリエティブディレクターという存在によって、それまでは単なる洋服や雑貨のデザインをしていたファッションデザイナーが、ブランドの店舗や広告をはじめブランドのイメージ全体をデザインする存在に生まれ変わったのだ。トム・フォードの天才はグッチ家の家族経営による行き詰まりと度重なるスキャンダル(パトリツィアによるマウリツィオの暗殺など)によって地に堕ちたブランドイメージを回復させ、急成長させた。
現在のスターバックスの中興の祖であるハワード・シュルツ(Howard Schultz,1953-)はイタリアのエスプレッソ文化に衝撃を受け、これをアメリカに導入したことによってスターバックスを急成長させたのに対し、トムフォードはテキサスの荒々しく力強さとイタリアの優雅さを見事に調和させることによってグッチを急成長させた。
イタリアの文化は期せずしてブランド資本主義を推し進める上で重要な役割を果たした。中国の台頭以前、日本はファッションブランドにおいて非常に重要な市場であった。そして、日本はブランド資本主義のロドス島だった(ここがロドス島だ、ここで跳べ!)。
スターバックスが進出した頃の日本は、世界展開を目指すコーヒー企業にとってはうってつけの条件が揃っていた。独自のコーヒー文化を発展させてきた文化的基盤、バブル期による消費社会の成熟と未成熟なコーヒー市場、そして日本人の「ブランド好き」、ブランディングとマーケティングによって、これらすべての条件をたくみに生かしたのがスターバックスとサザビーだった。
スターバックスは、日本についての知識を欠いたホテル業界と組んで一度失敗した。シュルツは再び戦略の見直しを迫られる。1995年にスターバックスのマーケティングの最高責任者となったスコット・ベドべリが、彼が「ザ・ビッグ・ディッグ(The Big Dig)」と名付けた計画によって、マーケティングの乗り出した。この計画によって得られたのは、スターバックスのブランドの核となるものが、コーヒーそのものではなく、コーヒーが与えてくれる体験を提供することであるという結論だった。
これによって、スターバックスは単なるコーヒーショップではなく、「ブランド」として自らを構築していく道を模索し始めることとなった。
シュルツは自らのリーダシップによって人を引っ張っていくというよりも、自らのブレーンに優秀な人材を配置することによって彼らのアイディアを取り込み、巧みなブランディングを可能にしたのだった。元々はコーヒー豆の品質を重視していたスターバックスが、人重視の経営方針にシフトしたのも、1989年に入社したハワード・ベアー(Howard Behar)のアイディアによるものだった。
ちょうどこの時期に、カリフォルニア州ロサンゼルスのスターバックス店を訪れ、スターバックスの可能性を読み取った角田雄二と鈴木陸三が、シュルツに手紙を送ったことが、スターバックスとサザビーの提携のきっかけとなった。このことは梅本龍夫(2015)『日本スターバックス物語──はじめて明かされる個性派集団の挑戦』に描かれているとおりである。
スターバックスが日本に一号店を出した年に、ファッション業界ではその後のブランド買収合戦を予告するように、LVMHモエヘネシー・ルイヴィトンのベルナール・アルノー(Bernard Arnault,1949-)がジバンシーのデザイナーであったジョン・ガリアーノ(John Galliano,1960-)をディオールのデザイナーに、そしてまだ駆け出しであったアレキサンダー・マックイーン(Alexander McQUEEN,1969-2010)をジバンシーのデザイナーに起用する。ファッションデザイナーがスターとして、ブランドの顔として表舞台に露出する、そしてファッションブランドが打ち出すイメージを消費者が鏡写しにすることよって、自らのアイデンティティを形成する。ファッションブランド市場が急成長し始めたのがこの時期であり、それと連動するようにして「スペシャルティコーヒー界」で最も早くブランド化に成功したのがスターバックスである。
事業の90%をテイクアウトを占めるスターバックスは、日本市場では成功しないだろうと見られていた。しかしブランドとは、見られる「まなざしの欲望」と一体となっているため、フラペチーノのようなこれまでになかった「映える」飲料は、ブランド好きの日本人が街中で見せびらかしながら飲みたがるような飲料であっただろう。
「ザ・ビッグ・ディッグ」によって得られた「ブランド」としてのスターバックス像、そのブランドイメージに最もふさわしい提携先としてのサザビー、日本の市場。すべての条件がうまく噛み合わされり、日本で大成功を収めたスターバックスは、サザビーから多くを学んだブランディングとマーケティングの手法によって、次々に世界展開していくのである。
スターバックスとイタリア
「美は痙攣的なものであるに違いなく、さもなくば存在しないだろう。( la beauté sera CONVULSIVE ou ne sera pas.)」というアンドレ・ブルトン(André Breton)の警句は、まさにイタリアにふさわしい。イタリアの文化はそれを見るもの触れるものに眩暈を与える。1983年に、シュルツはイタリアのミラノで開かれた国際家庭用品のトレードショーに出張した。この退屈な展示会から一歩外へと出たシュルツの目に映ったものは、客との会話を楽しみながらもよどみなくエスプレッソを抽出するバリスタの芸術的な所作だった。シュルツがイタリアの文化に受けた衝撃はスタンダール・シンドローム(Stendhal Syndrome)と呼ぶにふさわしいものだった。彼がイタリアから受けた衝撃はエスプレッソ文化にとどまらず、家族の延長のような人と人との結びつきを可能にするカフェの空間にも衝撃を受けたのだった。彼はそこに「顧客との絆」を見て取り、やがてそれをブランディングの柱に据えることになるだろう。
「スターバックスには肝心なことが欠けていたんだ。完全に見落としていた。とても重要な問題だと僕は思った。顧客との絆を見落としている」
John Simmons(2004).The Starbucks Story: How the brand changed the world.(ジョン・シモンズ 小林愛(訳)(2004).『スターバックスコーヒー―豆と、人と、心と。 (THE BRANDING) 』ソフトバンクパブリッシング株式会社.p62)
シュルツがミラノに出張した1980年代のイタリアは、「ミラノの3G」と呼ばれるジョルジオ・アルマーニ(Giorgio Armani,1934-)、ジャンフランコ・フェレ(Gianfranco Ferré,1944-2007)、ジャンニ・ヴェルサーチ(Gianni Versace,1946-1997)が、イタリア特有の華美な装飾性を実用性に落とし込んだスタイルによってミラノのモードシーンを牽引していた時期だった。同時期にラルフ・ローレン(Ralph Lauren,1939-)やカルバン・クライン(Calvin Klein,1942-)が、その都会的なスタイルでニューヨークのモードシーンを牽引していた。1986年にラルフ・ローレンがフランスのパリにアメリカ人デザイナーとして初めて路面店を出店し、1989年にジャンフランコ・フェレがフランス人以外のデザイナーで初めて、フランスのビックメゾンであるクリスチャン・ディオールのチーフデザイナーに就任したことからも分かるとおり、ミラノやニューヨークがパリと並ぶような流行発信地として注目され始めた時期だった。このような下地が、イタリアとアメリカのファッションの最良の部分を見事に融合させることによって成功した、グッチのトムフォードの登場を準備したと言えるだろう。
トム・フォードはアメリカのテキサスや1930年代最盛期ハリウッドのイメージをイタリアのファッション文化に融合させることによって、見事に成功を収めた。トム・フォードは極めて主張の強いデザイナーであり、女性モデルの陰毛をGマークに剃毛するような際どい広告(グッチ2003年春夏キャンペーン)により、ブランドイメージを全面に打ち出して消費者を魅了した(ちなみにこの広告で男性モデルが着ているスカジャンに刺繍されているのは日本の春画のモチーフである)。
他方で、シュルツは広告宣伝費に巨額を投資するよりも、口コミで、あるいはセレブを利用したあざとい宣伝手法で人々を捉えた。このような宣伝手法がとられたのはもちろん、トム・フォードのグッチが一部の顧客に向けた高級ブランドで、スターバックスが大衆向けの手に届く贅沢を提供する(これはサザビーのビジネス展開と合致している)カフェであることが一番の理由である。
この意味で、シュルツはトム・フォードのように明確な価値を打ち出すことによって人々を惹きつけるカリスマではなく、「絆」や「信頼」によって人々を取り込む優秀なセールスマンというべきである。シュルツのスターバックスは自らが創造したものによって人を惹きつけるというよりも、他の人や企業が創造したものをたくみに回収することで成長してきた企業と言える。そう考えれば、スターバックスのあり方がよく見える。
その一つの代表例が、スターバックスの看板商品であるフラペチーノ(Frappuccino®)である。
1994年スターバックスはジョージ・ハウエル(George Howell,1945-)のザ・コーヒー・コネクション(The Coffee Connection)を2300万ドルで買収する。この買収によって、1992年にザ・コーヒー・コネクションが商標登録していたフラペチーノの商標を手にしたことは、スターバックスの世界展開に大きく貢献した。
スターバックスの日本進出、そしてそれを足掛かりとした世界展開は、フラペチーノの展開とほぼ同期している。おそらくフラペチーノがなければ、スターバックスが現在のような世界規模のコーヒー会社になることはなかっただろう。
スターバックスはコーヒーの大量流通を目的として、1994年にペプシ(PepsiCo)と業務提携を結んだ。スターバックスとペプシの合資会社である「ノース・アメリカン・コーヒー合資会社(North American Coffee Partnership (NACP))」を設立し、ボトル入りのRTD(Ready-to-Drink)の開発に乗り出した。その最初の成果である「マザグラン(Mazagran)」というコーヒーソーダだった。
スターバックスのコーヒーとペプシコーラを足して二で割ったようなこのコーヒーソーダは、市場での受けが悪く、すぐに販売中止となる。そこで目がつけられたのが、スターバックスで売れ行き好調だったフラペチーノだった。スターバックスのフラペチーノ同じ味のフラペチーノを開発し、1996年にこれをペプシの生産ラインで製造し全国に流通させると、販売中止に追い込まれるほどの売れ行きを示した。このことからスターバックスはこの商品の生産のために巨額を投資した。そして、この商品は、1997年夏にはアメリカ全土のスーパーマーケットで販売されることとなった。
ここで重要なのは、スターバックスの大躍進がフラペチーノによるものであったにも関わらず、スターバックスは高品質のコーヒーを世界に広める企業であると言い張ったことである。
われわれには違いがわかるのだ。スターバックスの関係者は、素晴らしいコーヒーの味を知っている。本物のコーヒーこそがスターバックスの売り物なのである。それがスターバックスをスターバックスたらしめているのだ。
Howard Schultz, Dori jones Yang(1997).Pour Your Heart Into It: How Starbucks Built a Company One Cup at a Time.(ハワード・シュルツ、ドリー・ジョーンズ・ヤング 小幡照雄・大川修二(訳)(1998).『スターバックス成功物語』日経BP社.p331)
シュルツのこの言葉を信じるのであれば、スターバックスのアイデンティティは本物のコーヒーを販売することにある。実際、シュルツは高品質のコーヒーを世界に広める役割を担っていると信じていたのであろう。