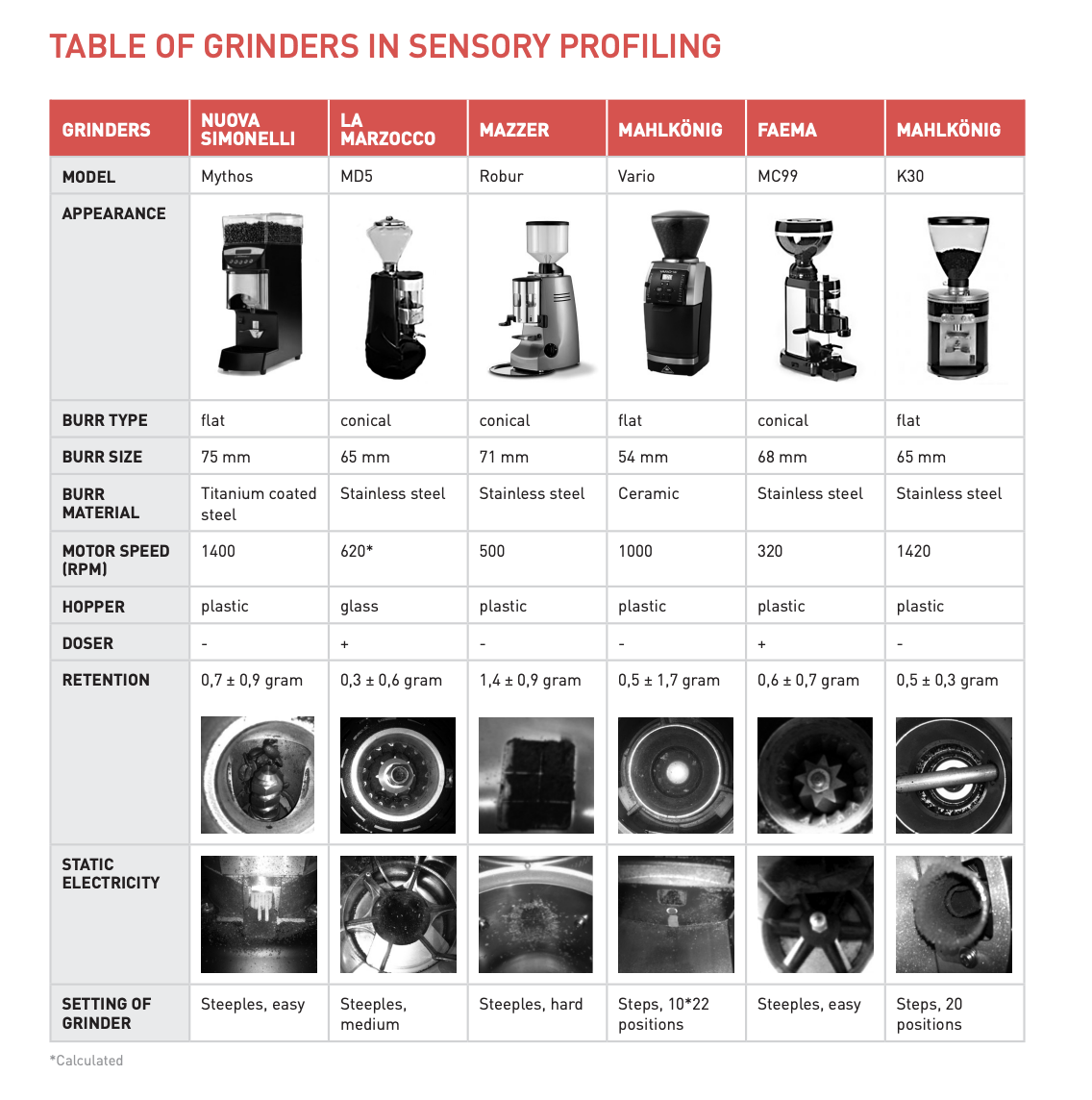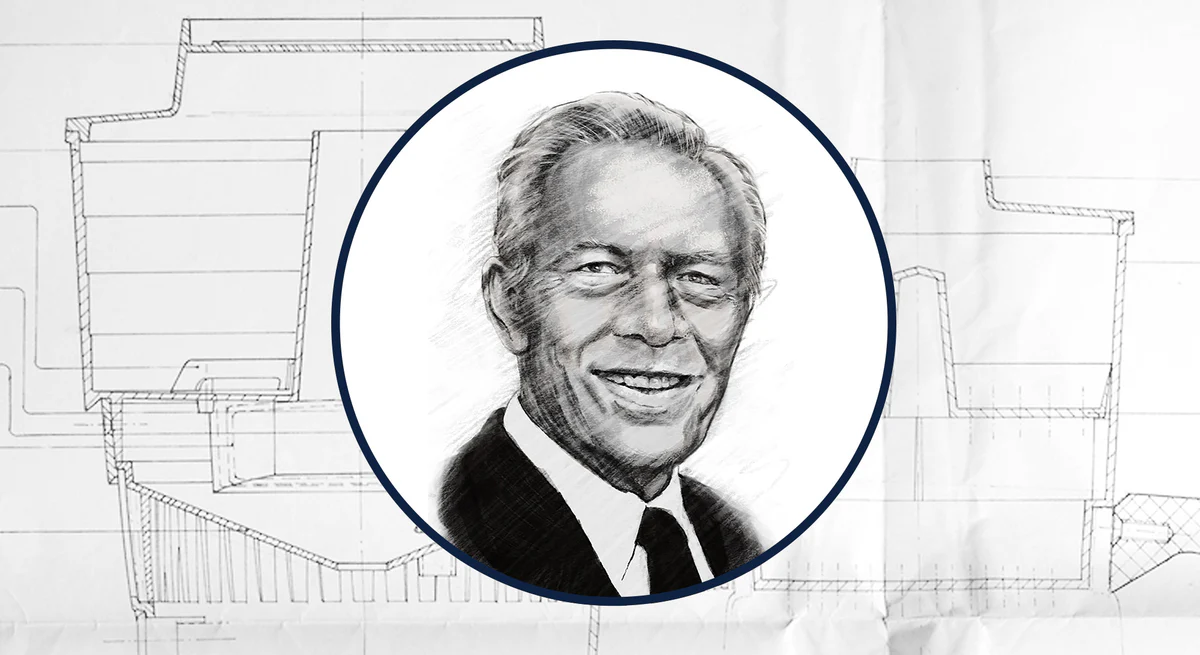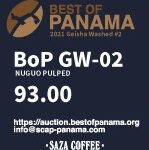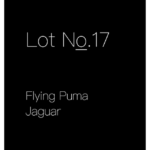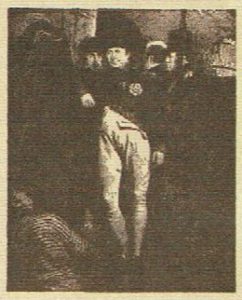コーヒーの抽出理論とその変遷 ネスプレッソの革新と陳腐
ネスプレッソの革新と陳腐

1975年、スイス・ヴヴェイのネスレ本社に入社したエリック・ファーヴル(Eric Favre)は、家庭でもイタリアのエスプレッソバーのような品質のコーヒーを簡便に楽しめる機械の開発を命じられた。当時、家庭用コーヒーは手間のかかるドリップ式か、風味が劣るインスタント式に限られており、その中間となる選択肢は存在していなかった。
同年、ファーヴルはローマを視察中に、パンテオン近くのサンテウスタキオ・イル・カフェ(Sant’Eustachio Il Caffè)という人気店に出会う。そこで彼は、店のバリスタがピストンを繰り返し押し込むことで空気を多く取り込み、挽いた豆の酸化を促進させ、豊かなクレマを生み出していることを知った。この観察が、後のネスプレッソ技術の核心的発想となったのである。
スイスへ戻ったファーヴルは少人数のチームを率い、カフェの抽出工程を家庭向けに再現する機械の試作を開始した。彼の構想は、挽いたコーヒー粉を密封して鮮度を保つ小型カプセルを用い、高温高圧の湯を針のようなノズルから注入することで、自動的に理想的な圧力と泡立ちを実現するというものであった。当時から「カプセルコーヒー」という概念自体は存在していたが、それを機能的な商品として成立させたのはファーヴルと彼のチームであった。
翌1976年、ネスレはこの新しいシングルサーブ式コーヒーシステムの特許を出願した。これが「ネスプレッソ(Nespresso)」の原型であり、その後10年間にわたり試作と改良が続けられた。ヴヴェイのネスレ本社内には、現在も当時の試作機が展示されており、配管やタンクを複雑に組み合わせたその姿から、技術開発の難航ぶりをうかがうことができる。
製品化までの道のりは平坦ではなかった。当時のネスレはチョコレートや粉ミルク、シリアルなどの大衆消費財を主力とする企業であり、家庭用高級コーヒーという発想は社内でも異端視された。インスタントコーヒーの市場を自ら侵食する懸念もあったためである。
こうした内部の反対を押し切り、10年後の1986年ようやくネスプレッソは市場に投入された。初期モデルは大型で、現在のような洗練されたデザインとは程遠く、カプセルも4種類しかなかった。主な販売先はオフィス市場であり、スペースの制約を受ける企業向け商品として位置づけられたが、期待された成果は得られなかった。
転機は1988年に訪れた。ネスレは新たなリーダーとしてフィリップ・モリス在籍時に衣料ブランド「マルボロ・クラシックス(Marlboro Classics)」を創出したタバコ業界出身者、ジャン=ポール・ガイヤール(Jean-Paul Gaillard)を採用し、ブランド戦略を抜本的に刷新した。ガイヤールはマシンの価格を引き下げ、ターミックス(Turmix)、クルップス(Krupps)、アレッシ(Alessi)といった外部メーカーとのライセンス提携を進めて家庭市場へ転換を図った。彼は収益源をマシン本体からカプセルへと移行させた。彼は「コーヒー界のシャネル」を標榜し、ネスプレッソを高級ライフスタイルブランドとして再定義したのである。
最も革新的だったのは、個人顧客を対象とする「クラブ・ネスプレッソ」の創設であった。カプセルを購入する顧客が同時にクラブ会員となり、嗜好データを蓄積しながら、ブランドへの帰属意識を持つ消費者共同体を形成していった。この戦略により、ネスプレッソは単なる家庭用コーヒー機器ではなく、「洗練された体験」の象徴へと変貌した。
1990年代に入ると、ネスプレッソは欧州を中心に徐々に拡大していった。1998年に初の公式ウェブサイトを開設し、2000年には最初のブティックをオープンした。翌2001年、中国のWTO加盟によりマシンの製造コストが下がると、事業は一層の拡大を遂げた。ちょうど同時期、スターバックスが欧州各地に進出し、エスプレッソ文化が一般化しつつあったことも追い風となった。家庭で「カフェの味」を再現したいという消費者心理に、ネスプレッソは完璧に合致したのである。
2006年、俳優ジョージ・クルーニーを起用した広告キャンペーンが始動し、ブランドイメージは頂点に達した。洗練・ユーモア・国際性を兼ね備えたクルーニーは、ネスプレッソの象徴として世界中で親しまれるようになった。同年、売上は5億ポンドを超え、2010年には30億スイスフラン(25億ポンド)に達した。ネスプレッソはコーヒー市場の一分野を超え、独自のカテゴリを創出したのである。
しかしこの成功の裏には特許戦略があった。ネスプレッソのシステムは特許によって厳しく保護され、長年にわたり互換カプセルの参入を阻止していた。だが1992年に取得した主要特許が2012年に失効すると、同社は各国で特許訴訟に敗北し、競合他社の参入を許す結果となった。市場は急速に多様化し、ネスプレッソは初めて独占的地位を失った。
以後、ネスプレッソはビジネスモデルを閉鎖的な専用システムから、持続可能性と品質を前面に出す方向へと転換した。CEOジャン=マルク・デュヴォワザン(Jean-Marc Duvoisin)のもと、アルミニウムリサイクルや倫理的調達を重視した「責任あるコーヒー」としての再ブランディングが進められた。一方で、カプセル廃棄に伴う環境問題が注目を集め、リサイクル率の低さが批判を呼んだ。これに対処すべく、同社は資源大手リオ・ティント社(Rio Tinto)との提携により「持続可能なアルミニウム」使用を推進している。
2010年代後半には、米国市場への本格進出を視野に「ヴェルトゥ(Vertuo)」システムを開発し、巨大なカップでコーヒーを飲む文化に向けて、より大容量抽出が可能なモデルを導入した。2015年、クルーニーは北米市場の広告にも登場し、ブランド認知が大幅に向上したが、米国市場における先駆者であるキューリグ(KEURIG)Kカップの長く暗い影に覆われた存在であることに変わりはない。
ネスプレッソはリサイクル拠点の拡大や「持続可能なアルミニウム」の採用など対策を進めたが、依然として年間数千トン規模のアルミ廃棄が指摘されている。社会的イメージの悪化は、同社の象徴であったクルーニーの広告戦略すら修正を余儀なくし、2020年代の新キャンペーンでは彼の姿が消え、「倫理的コーヒー」「思いやりから生まれる卓越」というテーマが前面に出るようになった。
また、企業としての成長は続いても、ブランドの輝きは失われつつある。ネスプレッソが一世を風靡した「高級で均質なコーヒー」という物語は、サードウェーブコーヒーの隆盛とともに時代遅れの象徴となった。いまやネスプレッソマシンを持つことは、かつてのように「先端的なライフスタイル」の証ではなく、「手軽さを重視する大衆的選好」の表れと見なされる傾向がある。
競合他社は自社製のプラスチック・生分解性・再利用型カプセルで市場を細分化し、ネスプレッソの優位性は揺らいでいる。グローバル化によって世界中に広がったブティック網も、主要都市では過密状態となり、かつての特別感を失った。顧客はいまやネスプレッソをルイ・ヴィトンやディオールではなく、一般的な家電ブランドと比較するようになっている。