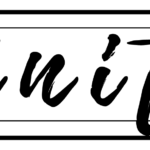以下、オビエド大学の川村 やよい(Yayoi Kawamura)とアメリカ博物館のレティジア・アルベテラ・ミラ(Letizia Arbeteta Mira)による「コーヒーサービス:ルイ14世の宮廷における日本の漆の存在」(原題:Un service à café : présence du laque japonais à la cour de Louis XIV)の日本語訳である。
川村 やよい、レティジア・アルベテラ・ミラ「コーヒーサービス:ルイ14世の宮廷における日本の漆の存在」
コーヒーサービス:ルイ14世の宮廷における日本の漆の存在
本稿の目的は、17世紀後半にルイ14世の宮廷で使用された、金で装飾された日本の漆のコーヒーサービスについて報告し、18世紀に頻繁に使用されるようになった金で装飾された日本の漆のヨーロッパにおける最初の例の一つとして分析することである。このような作品がフランスの宮廷にあったということは、日本の漆器がヨーロッパに入ってくるのはオランダの港だけだと思われていたため、その貿易ネットワークに疑問を投げる。
研究対象の分析

マドリッドのアメリカ博物館には、2006年に発見された日本の漆塗りの木製コーヒーセットが所蔵されている。セット内容は、トレイ1個、コーヒーポット1個、カップ4個、ソーサー4個である。蓋のつまみは、放射状のアカンサスの葉に囲まれたザクロの形をしており、全体が金で成形されている。縁も金で葉や楕円形の古典的な装飾が施されている。ソーサーの縁にも同様の金細工が施されており、1660年代以降の17世紀後半を彷彿とさせるスタイルとなっている。
このセットは、1700年から1746年までスペイン王であったフィリップ5世(Philippe V)が、父であるルイ・ド・フランス(1661年~1711年)から受け継いだ最初の宝石目録に掲載されているコーヒーサービスと間違いなく一致する。1734年に監査役会の大臣であるフアン・アントニオ・ダビラ(Juan Antonio Dávila)が作成した文書には、赤い「シャロル(Charol)」10点セットが記載されている。
18世紀のスペインで頻繁に使われていた「シャロル」(ワニス)という言葉は、極東の漆を指す。実際に、この10点は日本の「漆」が使われている。木の芯は精巧に旋盤加工され、何層もの漆で覆っており、主な層には布も含まれていると思われる。この作品は、食器として使用されることを前提としており、純粋な美的感覚で楽しむものではなかったが、しっかりとした作りになっている。
日本の漆は、Toxicodendron vernicifluum(旧称:Rhus vernicifluaまたはvernicifera)という木の樹液を主な原料としている。主成分はフェノール類のウルシオール(C21H32O2)で、湿度の高い空気の中で酸素と接触すると硬化するという特徴がある。
「漆」を塗ったものは、アルカリ、塩、酸、アルコールに非常に強く、吸湿性もほとんどない。また、お湯にも影響されない。そのため、今回のコーヒーセットのように、テーブルウェアに最適な素材といえる。しかし、何度も漆を塗り重ね、磨き上げ、乾燥時間を置いていくという、漆職人にとっては非常に根気のいる作業である。その結果、高い耐性だけでなく、何よりも深みのある輝きと心地よい温かみのある質感を実現している。しかし、紫外線を浴びると輝きが損なわれてしまうため、有害である。
鉄の酸化によって得られる黒漆は、最も安定したペーストであり、日本の漆芸術の主要な素材である。このコーヒーセットは、黒漆を何度も塗り重ねた後、辰砂(硫酸水銀)を加えた赤漆で仕上げられている。サービスの端や、特にトレイの裏面に黒漆が見えており、赤い層が保存されていない。
このコーヒーセットを構成するピースは、日本ではもともとこの目的のためにデザインされたものではない。 垂直方向の端が少ない四角いトレイである「懐石盆」は、日本の伝統的な食卓によく見られるもので、さまざまな料理や器を置くためのディスプレイとして使われる。コーヒーポットと思われる作品は、円筒形の本体と、それに平行して細長い取っ手が付いており、注ぎ口は短く、ほぼ平らな蓋は、容器の内側にある止め縁によって容器の開口部に収まっており、「のせ蓋造り」と呼ばれる仕組みになっている。これは、日本ではお湯を入れるための「湯桶」と呼ばれる容器である。取っ手のないカップは「椀」というボウルに相当する。僅かに広がった壁の先には「面取り」と呼ばれる面取りがあり、ボウルの底との接合部を形成してる。日本の社会では非常に一般的なモデルで、このタイプの「椀」は茶人の金森 宗和(1584年~1657年)が好んでいた。日本のボウルである「椀」には通常、蓋が付いているが、蓋の直径は椀の開口部の直径と同等かそれ以下であり、ここにはない。カップを載せるソーサーは、そのために用意されたものではない。連続した輪郭を持ち、カップを支えるための端がない。ボウルの開口部よりも直径が大きいため、蓋とは言えない。これは実際には、料理を盛るための低めの器「平椀」である。これらの作品は、現在も日本で「漆」を使って作られており、形もほとんど同じである。
17世紀に日本で作られた漆器の中には、よく似た形であるが湯桶に金色の「蒔絵」が豊かに施されたものが残っている。それは有名な花嫁道具に含まれていた作品である。「獅子牡丹」と「初音」のセットで、それぞれ1620年代と1630年代のものである。 このような単色の湯桶は、国内市場向けの一般的な作品だった。
日本でヨーロッパ向けに作られた17世紀の黒漆塗りの家具に金メッキの蒔絵が施されたものが、ヨーロッパでは数多く見られる。これらの作品は、VOC(Vereenigde Oost-Indische Compagnie)がチャーターした船で、オランダ人によって運ばれた。東インド会社の家具は、1630年代から17世紀末までのもので、そのスタイルは「絵画的」または絵のように美しいと表現されている。17世紀のヨーロッパでは、このような家具が数多く登場し、輸入された漆器は絵のように美しいと言われていた。しかし、このコーヒーセットは別のリアリティを感じさせる。1640年から1854年の間、中国とオランダに独占されていた日本唯一の国際貿易拠点である長崎港からは、日本の日常生活で使われる「漆」の漆器も出ている。ドイツのゴータ市にあるシュロス博物館に保存されている、私たちとほぼ同じ湯桶が、この事実を裏付けている。それは同じ寸法で、同じ「漆」の赤の仕上げの質感を持っている。私たちはこの作品は同じ工房で、ほぼ同時期に作られたのではないかと推測している。ゴータ市の博物館の例では、付加的な装飾はない。

ドレスデン(ドイツ)の絵画館(Gemälde Galerie)に所蔵されているジャン=エティエンヌ・リオタール(Jean-Étienne Liotard)の絵画も、日本の国産漆器がヨーロッパに渡ったことを示す間接的な証拠となるだろう。「ラ・ショコラティエール(La Chocolatière)」と題された作品では、四角い漆塗りのトレイを持った少女が描かれている。トレイはマドリッドのコーヒーセットのものとは少し異なり、縁が傾斜している。色は黒で、金のモチーフが施されている。その外観は、より一層ロココ調のテイストにマッチしている。日本のモデルをベースにしたヨーロッパ製の作品かもしれない。いずれにしても、日本で日常的に使われていたこの種の盆が、18世紀にはヨーロッパに輸入されていたことを、リオタールの絵が証明している。

ドーファン(王太子)の「宝物」にある金の装飾が施された「漆」

「シャロル・エンカルナド」(赤いニス)のコーヒーセットは、1689年にドーファン(王太子)が所有していた宝物の目録には記載されていない。しかし、前述のよう1734年に作成された、フィリップ5世が受け取った遺産の最初の目録には登場している。このように価値のあるものを相続することは、「ドーファン(王太子)の宝物(Trésor du Dauphin)」として知られている。このサービスは、「ドーファン(王太子)の宝物」がシャルル3世が設立した王立自然史庫(Real Gabinete de Historia Natural)に引き渡された1776年の目録にも記載されている。1809年にナポレオン軍がこの宝石を略奪し、1816年になって自然科学博物館運営委員会を通じてスペイン国に返還された。1839年に、この「宝物」はプラド美術館(Museo Nacional del Prado)の一部となり、現在も展示されている。しかし、その移転の間に、コーヒーセットは2006年にアメリカ博物館(Museo de América)で再び展示されるまで、姿を消していた。
金の装飾が施された日本の「漆」のコーヒーサービスは、いつの間にか他の「宝物」と分離されていた。これは、サービス自体の性質によるものかもしれない。「ドーファン(王太子)の宝物」は、非常に特別な特徴を持っている:それは、宝飾品や銀製品のグリプティックとして分類された作品ー半貴石、貴石、貴金属で作られた、つまり「金」として分類されている品々で構成されていることである。このアンサンブルでは、日本の漆塗りの木が、よりソフトで壊れやすい素材であるため、他の宝物の冷たくて堂々とした存在感と強いコントラストをなしている。
これこそが、1813年にマドリッドを放棄して、スペインのブルボン家の財宝の一部をフランスに持ち込もうとしたフランス軍が、当初興味を示さなかった理由である。漆のサービスが最終的に戦利品に含まれたのは、金の装飾のためだった。その繊細さにもかかわらず、急いで脱出し、災難に遭い、パリまでの長い旅に耐えた。しかし、苦難に遭った。1815年、スペインが盗まれたカップを回収した際、パリのスペイン大使館に提出されたメモには、金の金具の一部が失われたことが記されていた。
歴代の目録を詳細に読むと、その記述にはある種の矛盾があることがわかる:1746年の目録では、「サルビージャ(受け皿)」として記載されていたトレイは、「リッセ」、つまり装飾も付加物もないものとされている。1776年には同じものが、「アザファテ」(トレイ)と表現され、装飾もない。しかし、1815年には、上から2つの金の装飾品がなくなっていると思われている。
カップやソーサーも同様である。1756年には、4つのカップと脚部の装飾のみが記載されている。ソーサーや縁の装飾については何も語られていない。しかし、1776年のテキストでは、カップとソーサーのセット全体に、本体と底面に金の装飾が施されていたことが示唆されている 。1839年には、まだ2つのソーサーの底面に2つの金の網があったようだ。コーヒーポットについては、1815年に4つの装飾のうち3つとその鎖が失われているが、コーヒーポットには失われた装飾のためのスペースはないようである。
これは、私たちに伝わってきた金具に見られる特異な特徴によるものと思われる:漆塗りの木に圧力をかけて固定しているため、外しても木が痛まないようになっているようである。これは、この素材が非常に価値のあるものであったことを示しており、それを保護するために別の接合体系が考案されたのである。
金属部分を全体に適用したいということについては、さまざまな事情によるものだろうーその理由は、このようなデリケートな素材を保護し、傷をつけずに適応させ、同時にそのエキゾチックな特徴を維持する必要があったかーあるいは、ドーファン(王太子)の他のコレクションのスタイルに合わせる必要があったかのどちらかである。これは、金細工師の仕事によって、多数の異なる素材を統一することを意味する。いずれにしても、これはコレクションの中のエメラルドの花瓶のように、最も貴重な宝石と同じように扱われ、繊細な金の装飾が添えられていた。
単色の漆器は、あまりにも地味なので、当時の好みとしては間違いなく退屈なものだった。しかし、「漆」の人気は高く、所有者は金の装飾を加えて見栄えを良くしたいと考えていた。ここで重要なのは、「宝物」の他の作品の装飾に多く見られる銀ではなく、金が使われていることである。
金細工の細部を分析すると、2つの傾向が見えてくる。一つは、より古典的なものー中央に楕円形のある葉の装飾ーこれは、17世紀半ばまで使用され、1660年代に徐々に廃れていったパリ派のピーポッド(エンドウの鞘)や尖った葉のパターンをベースにしたものである。もう一つは、より現代的なものー葉と蓋のザクローこれは、ル・ブラン(Le Brun)やベラン(Berain)など、ヴェルサイユ宮殿の建築現場で働いていた芸術家たちが始めた、フランスの古典的なテイストの自然主義的な処理からインスピレーションを得たものである。1678年と1716年の間に活躍し、ドーファン(王太子)とドーフィン(王太子妃)(1660年~1690年)のためのオブジェの製作者であるピエール・ラドワロー(Pierre Ladoireau)のような、この宮廷関係者の金細工師が、「ドーファン(王太子)の宝物」のいくつかの作品を制作している。
この金の装飾が施され「漆」のコーヒーセットは、ヨーロッパにおける貴金属をあしらった小型の「漆」の器の最初の標本の一つである。アジアの作品を銀や金で装飾する習慣は、16世紀以降の中国の磁器によく見られる。その後、18世紀になると、日本の漆には美しく繊細な金や銀の装飾が施されるようになり、マリー・アントワネットのコレクションの中には、黒漆に金の「蒔絵」を施したものがある。18世紀のフランスの金細工師たちは、「蒔絵」の金彩とロココの美学を融合させようとした。しかし、コーヒーサービスは、このような美的衝動を共有していない。これは、17世紀のグラン・ゼクルス(大世紀)によく見られた、より落ち着いた、控えめな、そしてなぜかより深刻なスタイルを表現している。
フランスにおける導入のルート

コーヒーサービスそのものだけでなく、この10点がどのような経路でフランスに伝わったのかを考える必要がある。前述したように、これらの美学は、日本の輸出漆器の絵画的なスタイルとは一致しない。ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria & Albert Museum)に所蔵されている有名な「マザラン・チェスト」や「ヴァン・ディーメン・チェスト」などに見られるように、日本と貿易をしていたオランダ人は主にこのスタイルの漆器を入手していた。オランダ人は、ヨーロッパへの輸出を目的とした「エクス・プロフェッソ」に加えて、日本国内市場向けの日常使いの漆器も購入していたのではないかという疑問が湧く。しかし、別の仮説を立てることもできる:日本市場向けのこれらの部品は、長崎港で認可されたもう一つの外国人グループである中国人が入手した可能性がある。ー実際に中国では、赤漆の製品がとても人気があったことを無視できないだろう。そして、広東ー長い間、中国で外国人が利用できる数少ない港の一つであったーの市場に到着すると、これらはバタヴィア、そして最終的にはアムステルダムへと運ばれ、そこからルイ14世の宮廷やライプツィヒの見本市など、ヨーロッパの他の場所へと運ばれていったのではないだろうか。ヨーロッパに向けられた日本の漆器の取引に中国の商人が関与していたことは、マリー・アントワネットのコレクションの中のいくつかの作品を見ればよくわかる。イエズス会のジャン=バティスト・デュ・ハルデ(Jean-Baptiste du Halde)の文章もこの事実を強調している。17世紀にもこのような習慣があったことが推察される。
もう一つの可能性はシャム王国経由である。この可能性は、私たちが「宝物」のカタログを作成したときにすでに考察していたことであり、他の専門家も提唱していることである。O・インピー(O. Impey)とC・ヨーグ(C. Jörg)は、オランダ人がシャムに日本の漆器を出荷したことを記しており、その登録簿は日本人が日常的に使用していたものとして言及している;彼らは「フードボウル」と「日本人がフードボウルを置くフードトレイ」に言及しているが、これらはまさに私たちがここで分析しているタイプのものである。また、 1658年にパリで設立された中国、トンキン、コーチシナおよび隣接する島々の航海のための会社(Compagnie pour les voyages de la Chine, du Tonkin, de la Cochinchine et des îles adjacentes)や、1668年にシャムに工場を開設したことも考慮に入れる必要がある。フランスとシャムの関係は、1686年に贈答品として日本の漆器を数点を持ってきた、第二次シャム使節団がパリに到着したことで最高潮に達した。この会社は、シャムに滞在していたギリシャ人のコンスタント・ファウルコン(Constant Phaulkon)が、両国の関係強化を目指して設立した。O・インピーとC・ヨーグは、これらの日本の漆器は中国の商人を通じてシャム人が手に入れたと考えている;これは非常に妥当な仮説である。漆器のリストには、赤いニスのものが数点あるが、コーヒーサービスの10点は明確には同定されない。「日本の女性のための赤いニスの他のサービス」と書かれたものだけがこの説明に当てはまるが、化粧台のアイテムとして使用されたのがまさにこのサービスだったのか、それとも他のサービスだったのかはわからない。1949年にパリで出版された『シャム王の宮廷へのショーモンの使節の関係(Relation de l'ambassade de M. le chevalier de Chaumont à la cour du roi de Siam)』には、シャム王妃からドーフィン(王太子妃)への贈り物の一つとして記録されている。
いろいろな人への贈り物の中に、チョコレートがいくつかある。コーヒーポットの記載はないが、お茶を用意するための食器はある。17世紀初頭に西ヨーロッパに伝わったコーヒーとは、何の関係もない。もちろん、シャムとの関係はこの使節団だけではない;ルイ14世やその家族への贈り物も何度かあった。また、1668年にシャムにフランスの工場が開設された後、私たちが検討している今回の10点を含む、日本の漆の別のロットが到着した可能性も否定できない。
シャム経由の入国を裏付ける情報として、第二次使節団の後にルイ14世から派遣された大使で、シャムに1687年から1688年まで滞在していたシモン・ド・ラ・ルベール(Simon de La Loubère)が挙げられる。1691年に出版された彼の作品には、東アジアの漆器についての知識が示されている。彼は、「中国や日本の様々な作品に見られる美しいニスを作るガムを捨てる」漆の木について言及し、さらに次のように書いている。「また、日本から送られてくる赤いニスを塗った小さなカップは、その軽さに驚かされるが、これはカップの形をした布に、色を混ぜたガムを塗っただけのもので、中国ではラッカーやニスと呼ばれている」。日本が布や漆でカップを作っていたという間違いがあったとしても、彼の文章の中に「日本から送られてくる赤いニスを塗った小さなカップ」という表現があるのは興味深い。このフランス人はシャムに滞在中、日本から輸入された赤い漆のカップを目にしたが、これは私たちがここで分析するコーヒーセットのカップと非常によく似ている。
ルイ14世の宮廷で使われていたコーヒーサービス用の漆器
コーヒーに対する熱狂(アラビア語でk'awhah、元気という意味)は、アルコール飲料が禁止されていたイスラム世界で始まった。1475年にコンスタンティノープルで最初のコーヒーハウス「キバ・ハン(Kiva Han)」が開店し、それ以降、コーヒーを飲むことは単なる食習慣ではなく、社会的な儀式となった。実際に、コーヒーを仲間内で飲んでいただけで、商品名を冠した多くの建物は、いつしか当局から集会場とみなされ、悪い印象を与えてしまうようになったほどだ。それらは政治的不安定化の危険性を口実に閉鎖された:コーヒーの持つ刺激的なパワーが疑問視され、治療効果も考慮されなかったからだ。これらの事実は、新しさや味覚の変化を吸収する能力に依存していた外国の香辛料商人の目にすぐに留まった。
この流行の最初の知らせは、16世紀に東地中海から来た旅行者から西ヨーロッパに伝えられた。コーヒーは1600年頃、ベネチアの商人によって、薬効があるという名目でヨーロッパに持ち込まれ、その後、流行の飲み物として広まり、当初は「サラセン人の習慣」と見なされて拒絶されたものの、その独特の味で愛好者を獲得していったようである。その後、オスマン帝国がコーヒー豆の輸出を禁止するなどの事件があったが、1650年頃には確実に普及していた。
イギリスでは、1637年からコーヒーハウスがあったが、雑誌『ブリテン通報(Mercurius Britannicus)』に1652年に掲載された広告を見ると、食品の広告としては初めてと思われるほど、この飲み物はあまり普及していなかった。コーヒーは、朝と食後にカフェテリア・ジャマイカで提供される、強壮・治療効果の高い素晴らしい飲み物という目新しさで紹介された。
フランスでは、1664年にマルセイユ港がモカの最も選りすぐりの供給地となったことが記されているが、1669年には我々が扱っている歴史にとって重要な出来事があった。トルコの外交官、ソリマン・アガは、ルイ14世の宮廷にモカを紹介することに成功した。次々と招かれるたびに、目新しいものとして、豪華なディスプレイで紹介し、磁器のカップで提供した。最後に、ソリマン・アガは、外交上の誤解が飛び交うレセプションの中で、王によって迎えられた。
上流階級の人々は「トルコらしさ」を演出するために、食後に甘くしたコーヒーを飲んだ。それ以来、重税の負荷のため、高級品として扱われるようになった。一部の人々ーセヴィーニュ夫人もその一人ーは、このような奇妙な流行はすぐに過ぎ去るだろうと考えていたが、そうではなかった:1686年、パレルモ人のプロコップがパリで最初のカフェを作り、自らの名前を冠した。
しかし、宮廷の誰もが、王に認められていない飲み物を飲むことを口実に社交場を設けることができたと考えるのは酷である。そのため、宮廷用のコーヒーサービスの年代を決める際には、1669年を起点にするのが妥当だと思われるー王室用であればなおさらである。
コーヒーを飲むことは、イベントであり、公共の儀式であった。焙煎した豆を粉砕し、水で煎じて飲むというトルコ式の方法で始まったが、その強烈な苦味を嫌う人が多かったため、甘味料を加えた。そのためには、特殊な食器や器具が必要で、それらは時を経て現在の形に進化していった。
私たちは、フランス王室の社会的儀式の一部を記録することができた、なぜなら1689年にヴェルサイユ宮殿のドーファン(王太子)のキャビネットで発見された品々の中に、ここで扱っているサービスが記述されていなかったとしても、「デスク」の章では、「コーヒーデスク」と定義されているものがあり、これは引き出し、容器、湯沸かし器、抽出の準備に必要なすべてのツールを備えた、小さな豪華な家具である。
「19番、網と仕切り、銅製のバンドで装飾されており、側面には6つの小さな引き出しがある黒檀製の小さなコーヒーデスクは、引き出しが2つある台座の上に置かれた金色の水差しを持った2人の人物の上に、銅製のボウルが置かれている;胴体の中には、マーブル模様の銅製の花瓶の形をしたボウルがあり、そこには金メッキを施した風刺の効いた仮面があり、そこから水を出すための蛇口のようなものが出ている;その下には、同じ質と塗装の四角いボウルがあり、水を受ける役割を果たしている。デスクを開くとは2つの天板があり、そこにはコーヒーに必要な道具が入った引き出しがある。高さ2フィート半、長さ2フィート10インチ、幅1フィート10インチ。」
この構造は、1647年にデュラント(Durant)が設計した濾過機に類似していた可能性があり、その形態は、容器、蛇口、湯沸かし器を備えた18世紀後半の後続のものを彷彿とさせ、古風なモデルを踏襲している。
私たちが関心があるコーヒーポットだが、もし本当にコーヒーポットだとすれば、火の上に運ぶことはできず、内部にフィルターもない。そのため、贈呈用の容器となっている。つまり、火をつけるための容器だけでなく、飲み物を入れる容器としてのコーヒーポットも、17世紀後半のフランスでは、さまざまな形で登場したと言える。オスマン帝国時代のものは、一般的に金属製で、その当時の美意識とは異なるエキゾチックな輪郭であった。銀製のものはほとんど残っていないが、これはフランスで行われた大規模な鋳造の際に消えてしまったものである。カップとソーサーについては、持ち手のついたカップが登場するのは18世紀半ばであり、今回のサービスのようなボウルが使われていたようである。その際、深さのある受け皿を用意し、飲む前に冷やしてから飲むようにした。私たちのコーヒーセットには、まさにこのカップに近いソーサーが入っている。新しいエキゾチックな飲み物を発見していた当時の上流社会では、漆塗りの一連の食器がその日の気分に合わせたコーヒーセットになったと言えるだろう。
結論
ここで取り上げた漆製のコーヒーセットは、フィリップ5世の遺産であり、日本の生活の中で日常的に使われるものとして日本で作られた。しかし、ヨーロッパに到着すると、新しい状況に完璧に適応したーコーヒーという新しい飲み物に求められる、エキゾチックでユニークな容器となった。このような変化は17世紀末までに起こったと考えられ、このコーヒーサービスはフランスで最初に使用されたものの一つである。これらの漆器の日本からの輸入経路については、いくつかの仮説がある。シャム王国からのルートは非常に可能性が高いと思われるが、これまでシャム宮廷からの贈答品としての記録はなく、その他の出荷や贈答品としての記録もない。最後に、このセットは、日本の漆に金彩を施したものとしては、ヨーロッパで最も古いものの一つであり、おそらく最古のものである。