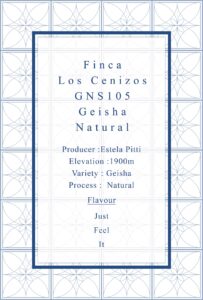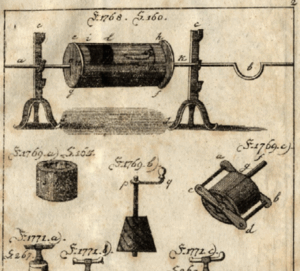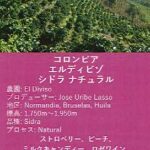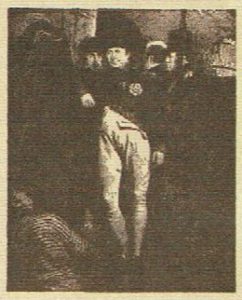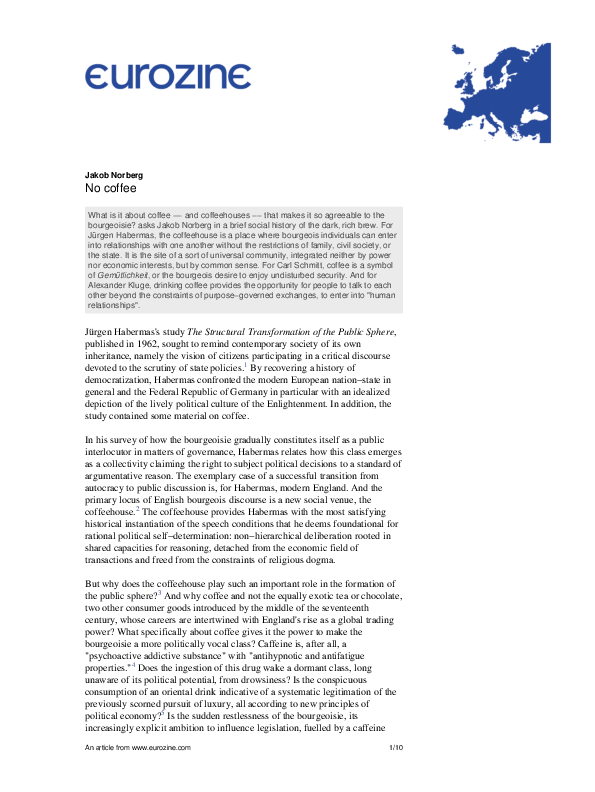
No Coffee:https://dukespace.lib.duke.edu/items/1f72ce3d-cd9d-476a-a3c2-18660988e806
ジェイコブ・ノルベルグ「コーヒーなし」
コーヒーなし
コーヒー――そしてコーヒーハウス――の何がブルジョワジーをこれほど魅了するのか? ジェイコブ・ノルベルグは、この濃く豊かな飲み物の簡潔な社会史の中で問う。ユルゲン・ハーバーマスにとってコーヒーハウスは、ブルジョワ個人たちが家族や市民社会、国家の制約なしに互いに関係を築ける場所である。それは権力や経済的利害ではなく、コモンセンスによって結ばれた一種の普遍的共同体の場だ。カール・シュミットにとってコーヒーはゲミュートリッヒカイト、すなわち平穏な安全を享受したいというブルジョアの願望の象徴である。そしてアレクサンダー・クルゲにとって、コーヒーを飲むことは目的主導の交流という制約を超え、人々が互いに語り合い「人間関係」に入る機会を提供する。
ユルゲン・ハーバーマスの1962年刊『公共性の構造転換』は、現代社会に対し、国家政策を批判的に検証する言説に参加する市民像という自らの遺産を想起させようとした。民主化の歴史を再構築することで、ハーバーマスは啓蒙主義の活気ある政治文化という理想像をもって、近代ヨーロッパの国民国家一般、特にドイツ連邦共和国と対峙した。さらにこの研究には、コーヒーに関する記述も含まれている。
ハーバーマスは、ブルジョワジーが統治問題における公的な対話者として徐々に形成されていく過程を考察する中で、この階級が政治的決定を議論的理性の基準に服従させる権利を主張する集団として台頭する様を論じている。専制から公的議論への移行が成功した典型的事例として、ハーバーマスが挙げるのは近代イギリスである。そしてイギリスにおけるブルジョワ的言説の主要な場となったのは、新たな社交場であるコーヒーハウスであった。コーヒーハウスは、ハーバーマスが合理的政治的自己決定の基盤と見なす言論条件——共有された理性的能力に根ざし、経済的取引の場から切り離され、宗教的教義の制約から解放された非階層的な討議——の最も満足のいく歴史的具体例を彼に提供した。
しかしなぜコーヒーハウスは公共圏の形成においてこれほど重要な役割を果たしたのか?そしてなぜコーヒーなのか?同様にエキゾチックな紅茶やチョコレート――17世紀半ばに導入され、イングランドの世界貿易大国としての台頭と運命を共にした二つの消費財――ではなく?コーヒーには、ブルジョワジーをより政治的に発言力のある階級へと変える力を与える、何か特別な要素があるのか?結局のところ、カフェインは「精神活性作用を持つ依存性物質」であり、「催眠防止・疲労回復作用」を持つに過ぎない。この薬物の摂取が、自らの政治的可能性に長い間気づいていなかった休眠状態の階級を眠気から覚醒させたのか? 東洋の飲み物の顕示的消費は、これまで軽蔑されてきた贅沢の追求が、新たな政治経済学の原理に従って体系的に正当化された証左なのか?ブルジョワジーの突発的な落ち着きのなさ、立法に影響を与えようとするますます露骨な野心は、カフェインの刺激によって煽られたものなのか?
精神刺激薬の歴史研究者たちは、コーヒーがブルジョワジーに受け入れられた理由を説明するため、コーヒーに様々な特性を付与しようとしてきた。コーヒーにはアルコールが含まれておらず、その解毒剤として、精力的な冷静さを保ち働き続ける手段として、容易に宣伝できた。これは初期資本主義の担い手たちの禁欲的倫理観に沿った性質である。この見解を裏付ける当時の広告資料は数多い。ピューリタン的コーヒー宣伝を引用し、歴史家ヴォルフガング・シヴェルブシュは「コーヒーによって合理主義が人間の生理学に侵入した」と主張する。その身体的効果は、絶え間ない警戒と活動への勧告と結びつけられる。
しかしハーバーマスにとって、コーヒーの化学的構成要素や活力を与える効果は、公共圏の形成において明白な役割を果たさない。マルクス主義的立場を持つ思想家として、彼は商品史というジャンルに内在するフェティシズムを回避する。そこでは消費対象が予期せぬ力を帯び、冒険的な物語の主人公となるのである。とはいえ、社会関係が商品資本主義からきれいに切り離せると信じるマルクス主義者はいない。ハーバーマスによれば、ブルジョワ的個人たちがコーヒーハウスで新たな関係性を築けるのは、家族・市民社会・国家の連関が資本主義的条件下で再構築されるためである。
社会全体の資本主義的再編成は、個人の社会的・経済的絆が主に契約形態をとることで、より流動的な人間関係を可能にする。市場経済は商業の主体が支配と隷属の社会的絆から独立して活動することを許すが、同時に家庭も生産と取引の場ではなくなる。その結果、親子からなる親密な家族円環は、生産ではなく相互の愛情と共感によって結ばれた自律的な個人群で構成されているように見える。解放された親密性の領域において、ブルジョワジーは新たな主観性の様式を発見し探求する。家族成員は感情に満ちた手紙や日記の読者・執筆者となる。この新たな経験のレパートリーに基づき、彼らは自らを規定された公的役割を超えた存在を持つ人間として構想し始める。
この人間的な親密さの私的領域は、他の社会領域から隔絶されたままではない。むしろ個人たちは、コーヒーハウスといった新たな場において互いに対話する。しかしそうした際にも、彼らは新たに獲得した自律的で平等な人間としての地位を保持し、かつて階級が誇示され確認されていた複雑な封建的儀礼の重荷から解放されている。ブルジョワジーの成員がコーヒーを飲むために集うとき、彼らは真の人間性の参加者として集うのである。特定の支持基盤や利害を代表するのではなく、普遍的な共同体を体現する存在として自らを主張する。実際、確立された枠組み内の特定集団ではなく、人間性そのものを代表すると主張するからこそ、彼らは政策問題に対する管轄権を自らに帰属させることが可能となるのだ。啓蒙された世論は政治権力行使を正当に抑制し得る。なぜなら封建的障壁に縛られない個人間の自発的交流を通じて展開される公共的言説においては、あらゆる懸念事項に優先して理性的な議論が支配するからである。
ハーバーマスの叙述によれば、英国のコーヒーハウスがブルジョワ政治影響力の主要な器官として成功した背景には、普遍的共同体の場として自らを提示する能力があった。余暇にコーヒーハウスに集う者たちは、権力でも経済的利害でもなく、コモンセンスによって結ばれている。しかしこの見せかけは排他的な入場政策によって支えられている。ハーバーマスはほとんど付随的に、冷静な理性の場としてのコーヒーハウスの評判が女性の排除を必要とする点を指摘する。コーヒーハウスは依然としてジェンダー化された空間であり、結局のところ「人間性」とはコーヒーを飲む男性たちを指すのだ。
ハーバーマスの英国のコーヒーハウスに関する記述は、多くの点で学術研究の枠を超え、一種の神話、奇妙なほどに喚起力のある歴史的モデルとなった。公共的でありながらリラックスした交流を特徴とする特定の場所と結びついた、活気ある知的文化という概念が私たちに共鳴するのは、それが今も認識可能だからである。我々はコーヒーを飲み、カフェで集い、友人や知人と談笑する。ハーバーマスの描くコーヒーハウスの姿は、今も日常の実践と符合する。『公共性の構造転換』は、解放された言説という規範的ビジョンと、ありふれた、ささいな日常体験を暗示的に融合させている。この融合こそが、対立を解決あるいは少なくとも括弧に入れる場としてのカフェに対する、過度に楽観的な熱狂の一端を説明している。スウェーデンの雑誌『アクセス』の近刊号で、ある寄稿者は「ヨーロッパのカフェはナショナリズムを癒せるのか?」と問う。民族・宗教的対立、差別、階級格差――これらも、コーヒーを囲んで集うことで、奇跡のように消し去られるかもしれない。
しかしハーバーマス自身は、啓蒙時代以降の公共圏の運命について、対面討論の場が連鎖する場としての見通しをむしろ悲観的に描いた。ブルジョワ的世論形成の媒体としてのコーヒーハウスの成功は、時とともに消滅した制度的前提に依存していたのである。自律的な個人が制限のない対話の中で共通の人間性を享受できる、国家と市場の間の仲介空間としての公共圏は、政府権威と商業企業との相互浸透が進むにつれて消滅する。資本主義企業はますます大きな権力を振るい、国家はそれらを相殺し個人にある程度の安全を保証するために責任を拡大するが、その結果生じる大規模企業と拡大する国家との相互作用は、効果的な自由な議論の余地をほとんど残さない。
伝統的に強力な行政機関と政治的に弱い中産階級を持つドイツにおいては、ハーバーマスが描いた合理的な討議の文化が、国家構造と市場の隙間に現れたかどうかさえ疑わしい。実際、ドイツの文脈ではコーヒーは少し異なる意味合いを持つ。それはしばしば特定の価値観——あるいは特定の雰囲気や気分——と結びつけられ、半家庭的な居心地の良さや快適さを意味するゲミュートリッヒカイト(Gemütlichkeit)という概念に凝縮されている。ゲミュートリッヒカイトは、はるかに控えめなブルジョワジーのモットーである。この階級は公共空間を真に征服することはなく、むしろ「陶磁器のストーブ、ドレープの掛かったポートリエ、トルコ絨毯、そして豪華なソファやアームチェア」で飾られた、よく遮断された応接室へと退却する。ドイツのブルジョワジーは豪華な家具の背後に自らをバリケードし、それによって公共世界の煩わしさから自宅を要塞化する。
法学者・政治理論家カール・シュミットは、戦後の辛辣な用語集の注釈で、ブルジョワの室内空間に漂う淀んだ空気を捉え、家庭という囲いの中で妨げられない安全を享受したいという願望の象徴としてコーヒーを指摘している:
フランス語: sécurité; ドイツ語(現在まで): Gemütlichkeit。これは内面化された―あるいは室内化された―と同時に世俗化された神の恩寵の保証であり、香ばしいタバコを詰めたパイプと一杯の美味しいコーヒーの前で恐怖と戦慄が終わる瞬間である。ルターとモラヴィア派が「安全」を官能性の実体として激しく非難した後、巧妙に隠された官能的享楽が再び現れたのだ。
シュミットの見解によれば、彼の記述で見事に描かれた典型的なブルジョワ的ペリシテ人は、快楽に対して禁欲的に反対しているというより、安全に――すなわち心配なく――享受できない快楽に対して警戒心を抱いているのだ。 コーヒーはタバコと組み合わさることで、危険を伴わない陶酔を象徴する。それは主体の自制心を危険なほど緩めることのない刺激物である。それは、豪華な快適さの安全地帯に安住する限定された自我を超越する動きを意味する恍惚とは区別される、ひそやかな至福を意味する。
しかしこの記述には、より広範な批判が込められている。シュミットは主張する——ブルジョワの室内における快適な生活は、その平凡で質素な性質にもかかわらず、人間を世俗的快楽への罪深い執着へと誘惑するのだと。その罪深さは安全の追求にある。防護されたサロンにおいて完全な安全状態を達成しようとする意志は、人為的ユートピアの可能性を信じる冒涜的な信念を露呈している。
シュミットの日記は厳格なキリスト教倫理の特異な表現に映るかもしれないが、彼はブルジョワジーを批判する長い列に加わっている。彼らは家族を超えた共同体を評価できないブルジョワジーを非難する。典型的なブルジョワ個人は、真の生活は私的領域で展開すると信じ、外界を異質で危険な領域と認識する。しかしブルジョアジーが政治的に行動する限り、それは家庭で育まれた安全への欲求に導かれ続け、世界を一つの穏やかな内面空間に変えようとする野心を抱く。ブルジョアジーにとって、対立は議論の継続的な流れを乱暴に妨げるものであり、そもそも起こってはならない。この時点で、ブルジョアの主人が平穏な会話の回復を呼びかける「どうか落ち着いて!(Nur immer gemütlich!)」あるいは「落ち着こう、落ち着こう!(Temper! Temper!)」という呼びかけは、ますます不気味に響く。
シュミットが、絶対主義時代以降政治哲学の語彙の中核をなす「安全」の概念を、日常的な「家庭の平穏」という概念と結びつける手法は、究極的には近代的ユートピアへの批判を示唆している。彼は、ブルジョアジーが政治プロジェクトにおいて、ゲミュートリッヒカイトに内在する価値観を、必然的に対立によって定義される政治領域へと転置していると主張する。神学的な観点から、これは冒涜に等しい。しかし同時に、彼は「世界的な内面」という認識されないビジョンが招く破滅的な政治的帰結にも言及する。対立は不要かつ無意味だと信じるブルジョワジーは、いかなる対抗者も認めようとしない。そして、セキュリテ(安全)という概念に結晶化された予め定められた社会的調和に抵抗し異議を唱える者は、排除され、単なる厄介者と見なされるのだ。
したがって、その平和的な性質にもかかわらず、ブルジョワジーは手強い敵となり得る。政治的概念に関する研究において、シュミットは、あらゆる特定の決定から自由な人間として自らを位置づけ、人類の名において行動すると主張するリベラル派に対して警鐘を鳴らしている。人類という用語は、対立によって構造化された空間における論争的立場を自覚した、真に政治的な主体を指すものではない。むしろ「人間性」の地位を独占する者は、敵対者を非人間として排除し、その殲滅に乗り出す。世界平和の維持という究極の安全追求——つまり完璧なゲミュートリッヒカイトによる地上楽園の構築——は、結果として潜在的な敵対者を最悪の方法で周縁化する。すなわち人間共同体からの排除によって。家族的価値観ほど危険なものはない。
ハーバーマスによれば、ブルジョワジーは儚くも有望な公共圏でコーヒーを消費する。シュミットによれば、彼らはブルジョワ的室内空間の偽りの調和の中でそうする。両思想家は結局、コーヒーを囲む者たちが、政治的不和や社会的制約の圧力から解放された人間として自らを認識する傾向を記述している。人は、あらゆる関係性を予め規定する文脈から切り離された空間でコーヒーを飲む。コーヒーブレイクの瞬間、通常は葛藤と不平等に彩られた存在を囲い込む条件は停止し、その結果生じる状態には健全な公共圏の原理、あるいは非政治的ゆえに致命的なユートピアの原理を見出すことができる。
作家であり映画作家でもあるアレクサンダー・クルーゲは、上述した二つの極点の中間的な立場にあると言える。彼の姿勢は、ハーバーマスの公共圏に関する博士論文が発表されたのと同じ1962年に出版された短編集『人生来歴』に収められた「ブーランジェ中尉」という物語に最もよく表れている。「ブーランジェ中尉」は、野心的な青年ブーランジェの波乱に満ちた経歴を描く。医学博士号取得に失敗した彼は、1942年にストラスブール帝国大学のヒルト教授の助手として働くことに同意する。その任務は凄惨なものだった――東部戦線でユダヤ系ボルシェビキ人民委員の頭蓋骨を調達すること。ブーランジェは捕虜の中から標的となるグループを隔離し処刑する任務を任される。教授の目的は、ソ連軍高官層にいるユダヤ人によって代表される「亜人種」の類型標本コレクションを完成させることであり、ブーランジェは学術キャリアへの転身を果たせなかった過去にもかかわらず、この特殊任務を引き受けることで「研究部門への異動」の可能性が高まると信じていた。
物語の大半は、ブーランジェが可能な限り臨床的かつ体系的に任務を遂行する様子の描写に費やされる。彼は捕虜となったソ連兵への尋問を通じて定義された集団に属すると見られる者を選別し、注射で殺害、首を切り落とし、特別設計の錫製容器に収めてストラスブールへ送る。パン職人であるブーランジェは、実際には「肉屋の職務」を遂行するために雇われていたのである。つまり、学界での望んだ昇進は実現しなかった。
しかし、本文の最終段落では、ほぼ20年後の1961年に起きた出来事が語られる。ブーランジェはケルンの製粉所で梱包作業員として働いており、目立たず、過去の職歴による法的追及を避けようとしていた。だが彼は忘れられてはいなかった。左派紙『ル・ユマニテ』のフランス人記者が彼を見つけ出し、インタビューを成立させるのだ。このインタビュー(その報告が中編小説の最終部を占める)で、記者はブーランジェがヒルト教授の助手時代に行った選別手法に焦点を当てる。彼はどのようにユダヤ・ボルシェビキ委員を見分け、どのように行動したのか?
こうして短編小説を締めくくるインタビューは、前半で支配的だった役割分担を逆転させる。1961年、ブーランジェはもはや潜在的な犠牲者への尋問を行う立場ではなく、権力の座から引きずり降ろされ、自らの犯罪関与について一連の質問を受ける側となった。その回答は、彼がナチス国家の機構にどのように関与していたかを明らかにすることになる。クルーゲの物語は一連の捜査的動きで構成され、テキストは犯罪者プロファイリングや尋問調の簡潔な言語で書かれている。これは終盤の短い節で最も顕著で、すべての発言が「質問」または「回答」と明記されている。
しかし支配的な尋問形式は、短い最終段落で崩れる。ジャーナリストが取材を終えながらも、まだブーランジェを去る準備ができていない瞬間だ。厳格に規定された質問形式にもかかわらず、二人の人間の間には何らかの形で躊躇いがちな出会いが生じており、記者もブーランジェも、調査の枠組みの外で会話を続けたいと望んでいる。非人間的カテゴリーにおける肯定的側面を記録しようとする行為そのものによって、人間としての主体性が既に否定された者たちと会話を交わしたブーランジェ自身とは対照的に、フランス人ジャーナリスト・インタビュアーは調査という形式を脱却し、別の対話形態を模索する。しかしこのより柔軟で平等な交流様式は即座に遮断される。両主人公が共にコーヒーを飲むことが叶わなかったからだ:
コーヒーなし:インタビュー中、B.と『ル・ユマニテ』紙の代表者[Vertreter]との間に人間的な関係が生まれた。インタビュー終了後、二人は一緒にコーヒーを飲みたいと思った。しかしそれは不可能だった。この時間帯、従業員が仕事を離れる口実を与えないため、カフェテリアではコーヒーが提供されていなかった。しかもカフェテリアでは誰も座ることが許されていなかった。こうしてB.と取材者はコーヒーを飲まずに別れた。
先行研究者は、ジャーナリストとブーランジェの間の人的接触が、最大限の効率化のために考案された厳しい職場規則によって発展させられないと指摘している。利益のために、組織的に偶発的な出会いが禁止されているのだ。会社のカフェテリアは、階層や生産の枠を超えた憩いの場であるコーヒーハウスとは程遠い。しかしこの解釈では、終結段落の批判的意図を十分に説明しきれない。現代産業資本主義に向けられた皮肉は、別の問題——すなわちブーランジェとの「人間的関係」の可能性/不可能性——の存在によって複雑化している。仮にブーランジェが考えを改め、ヒルト教授との関わりを後悔していたとしても、彼と腰を据えて共通の人間性を探求し確認できる余地は、いったいどれほどあるだろうか?
クルーゲは、ブーランジェとのより人間的な接触を試みることが許されない、あるいは不適切だと書いているのではない。それは「不可能」だと記しているのだ。調査ジャーナリストと元ナチス研究助手との間にある隔たり——そして実際に隔てられなければならない隔たり——を埋めることは不可能なのである。この解釈において、フランス人記者は左翼イデオロギーや侵略された国の代表であるだけでなく、ドイツ語テキストが宣言するように、人類(L'Humanité)の代表者[Vertreter]でもある。普遍的人類など存在せず、明確に階層化された異なる人種集団のみが存在するという前提に基づく研究プロジェクトに参加したブーランジェにとって、そのような大使すら認識できないかもしれない。
クルーゲの最終段落は読者に袋小路すら提示する。ブーランジェに対して「人類の代表者」の立場を取れば、自らが代表すると主張する本質を何らかの形で裏切らざるを得ない。一方で、ブーランジェに人間的な接触を認めることは、彼が恐るべき犯罪に積極的に加担した事実を覆い隠すことになる。彼は単一の人類共同体の存在を否定する仕組みの中で働き、彼が協力した研究は絶滅計画のための疑似科学的根拠を提供した。他方で、彼に人間的な関係を拒むことは、ある種の差別と排除を繰り返すことに他ならない。この状況は、クルーゲが記す通り「不可能」なのである。
この問題点は、一杯のコーヒーに関する一節に示唆されている。ジャーナリストがブーランジェとコーヒーを共にし、最も人間的な行為——すなわち仕事を中断し、特に意味のない雑談を交わすこと——に没頭する余地は存在しない。コーヒーは、尋問の制約やあらゆる手段的コミュニケーションの型から逃れる社交性の象徴として立ち現れる。一杯のコーヒーは、目的主導の交流の制約を超え、割り当てられた役割に内在する仕様から解放される機会を換喩的に示す。クルーゲはそうした機会への欲求を否定しないが、コーヒーブレイク中に解決できる問題や克服可能な分断とは何かと問う。ブーランジェとコーヒーを飲むことは困難、あるいは不可能である。
ハーバーマス、シュミット、クルーゲ:彼らの異なるテキストは、友好的な自律的相互作用の様式、そしてこの相互作用形態の潜在的な政治的内容と利用可能性について論じている。彼らの言説から浮かび上がるコーヒーの社会史は奇妙に思えるかもしれないが、結論には程遠い。現代の論評者たちも、拡大するコーヒー文化を社会における価値観の変容の表れとして読み解くことができる:
解体されたスウェーデン福祉国家[folkhemsbygget]には、国家が社会や労働以外の領域において一定の責任を負うという理念があった。[...] 今やこの責任は他の多くの事柄と同様に個人に委ねられており、実際に起きたことと言えば、コーヒーショップが増えただけだ。
「起きたことと言えば、コーヒーショップが増えただけだ」―ブルジョワ的社会的想像におけるコーヒーの役割を過小評価すべきではない。コーヒー飲用を囲んで生まれた特定の儀式や共食の行為は、確かにブルジョワ的生活において特別な位置を占めている:コーヒーは酩酊させず、むしろ労働を助長するが、それでも消費には短い休憩が必要だ; コーヒーを伴う会話は些細なものから深刻なものまで及ぶが、決して和解不能な敵同士の間で行われることはなく、有害な対立を中和する機会として提示される傾向がある。他人とコーヒーを飲むのは心地よいが、その行為自体は本質的に集団的な営みではなく、したがってそれは明確に分離可能な原子として捉える社会の概念を損なわない。したがってコーヒーハウスやカフェは、ブルジョワジーが歴史を通じて示してきた場所である。そこでは、純粋に経済的取引に必要な接触を最小限に超えた人間的交流を構想できることが示されてきた。ブルジョワ社会は、共同体が個人の利己的追求の副次的かつやや神秘的な効果としてではなく、何か別のものとして現れる場所を、少なくとも一つは許容していると言える。私たちはコーヒーを片手に、しばらくの間会話を交わすことができる。
しかし、国家が人間の社会的存在から撤退し始めて以来出現したすべてのコーヒーショップが、ハーバーマスが描いた公共圏——意見表明を望む者すべてが利用でき、階層や公的立場を考慮せず議論を展開し、耳を傾ける用意のある者たちのための討論の場——を体現しているかは不明である。コーヒーを飲むことはライフスタイルの選択を意味し、洗練された消費行為を通じて自己を構築する新たな事例を構成する:
コーヒーは今やワイン、ウイスキー、葉巻の仲間入りを果たした。巧妙なマーケティングと消費拡大が、見栄っ張りぶりを新たな高みへと押し上げた。[...] 単純なエスプレッソを注文するだけではもはや足りない。いや、むしろ「シェード・グロウン・コロンビア・ナリーニョ・スプレモ・デカフェ」でなければならないのだ。